企画記事
[レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/008.jpg) |
ビデオゲームにおける作家性とは何かという問題について,簡単に答えは書けない。ゲームにはさまざまな要素が混線しているせいだ。けれど,イギリスのゲームクリエイター,ジェフ・ミンター氏が40年近くにわたって生み出したゲームをいくつか遊んでみれば,それが何なのかは体感できる。
暗いディスプレイの中を禍々しく明滅する原色のピクセル。アーケードライクなゲームデザイン。サイケデリックな視覚効果。そして,ヤギとラクダたち。「Tempest 2000」をはじめ,ミンター氏のほとんどのゲームに共通する要素だ。
それらはことごとく普通のビデオゲーム評論を受け付けない。誰もがゲームデザインや,ストーリーや世界観の解釈をレビューするが,ミンター氏のゲームに至ってはあまり意味をなさないように思う。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/002.jpg) |
ミンター氏のゲームをプレイする際の感覚は,日本の美術における横尾忠則氏や田名網敬一氏の作品を見るような気持ちに近い。作品の文脈がどうだとか言えなくもないが,どんな言葉も作家の強烈な無意識が反映された作品の前にかき消される。そしてその無意識こそ,「作家性とは何か」を言語化する前に,プレイヤーが彼のゲームで体感するすべてといっていい。
無意識。ミンター氏のゲームデザインは,ありきたりなロジックを超えてしまうような発想のものが多い。そしてそれらのゲームは,時が経つにつれてさらに特異さを際立たせていくかのようだ。
ビデオゲームの文脈においては,テクノロジーが進歩し,ビジネスモデルも変化することによって,どんなに優れたクリエイターでも時代が変わればほとんどの場合クリエイティビティの変化を求められるものである。
ところが,ミンター氏に至っては自らの作風がいささかも崩れることがない。2020年代の今も,80年代に確立したビジョンからブレていないのだ。
ビデオゲームが新しいメディアとして隆盛を始めた1980年代から,産業としても技術としても表現としても拡大を遂げた2020年代の現在に至るまで,ミンター氏は独自のゲームクリエイターとして活躍し続けている。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/001.jpg) |
そんなミンター氏の異質さを評してか,彼を「最後のインディーゲーム作家」だと語るゲームがある。それが「Digital Eclipse」(PC / PS5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One)「Llamasoft The Jeff Minter Story」(以下,LTJMS)である。
本作はミンター氏が80年代から90年代にかけて開発したタイトルを年代順にまとめ,彼の出生からゲーム業界進出,そして作家としての地位を確立するまでの経歴を記したものだ。各時代を評した豊富なドキュメンタリー映像のほか,ゲーム開発にあたってのメモや発言も豊富に残されている。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/003.jpg) |
「LTJMS」の特徴は,まるで現代アート作家の大回顧展を見るかのように,ひとりのクリエイターの軌跡を体験できることだ。プレイヤーは自由にミンター氏のゲームをプレイしたり,資料を閲覧したりしながら,ミンター氏のクリエイティビティを探っていくことになる。
また,80年代〜90年代初頭のビデオゲームシーンの様子が伺える資料価値の高さも「LTJMS」の魅力だろう。ミンター氏が開発したタイトルのさまざまなバージョンをプレイできるのも重要なポイントとなる。
たとえばミンター氏の代表作であるシューティングの「Gridrunner」や,「Attack of the Mutant Camels」などの他機種への移植版やリメイク版がプレイできるのは貴重だ。機種ごとのスペックによってミンター氏の表現にどう差が現れたかも見どころである。
Digital Eclipseのキュレーションによる,歴史的な企画展としてのゲーム
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/005.jpg) |
「LTJMS」の面白さは,そもそものミンター氏の異質なクリエイティビティがどこから発生したのかを考察することにある。
現代アートの回顧展で作家の出生から今までの作品やメモ,評論家による解説を見ていくことで,観客が「あのアーティストの作家性はどこから来たものなのだろうか?」と考察するように,「LTJMS」は「ジェフ・ミンターとは一体どこから来たのだろうか」をプレイヤーに考えさせる。
そんな導線を用意した開発会社であるDigital Eclipseの仕事ぶりは特筆すべきだろう。
同社はもともと「Street Fighter 30th Anniversary Collection」や「Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection」など,人気シリーズをひとまとめにしたコレクションを作る企業だった。ところが近年,単なるコレクションから,美術の企画展のようなビデオゲームの製作に舵を切っている。
その皮切りが「Atari 50: The Anniversary Celebration」なのは間違いない。表向きはアタリ社の50周年記念コレクションなのだが,年代別にタイトルを並べるだけではなく,開発の資料のほか,関係者への豊富なドキュメンタリーを含める構成を取った。それによって単なる懐かしのコレクションではなく,一気に歴史的な展示としてのゲームへと変わった。
続く「The Making of Karateka」では,歴史を検証するアプローチとして過去の名作を扱う手付きが一段と洗練される。名作格闘アクション「Karateka」がどのように開発されてきたかを,クリエイターのジョーダン・メックナー氏のインタビューや開発資料を元にまとめあげている。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/015.jpg) |
このようにDigital Eclipseは「大企業の軌跡」から「名作が生まれた背景」といった企画展的なゲームを積み重ね,「LTJMS」ではついに「異色のクリエイターの作家性とは何か」を特集するようになったのである。それゆえに,同社の過去作以上に作家の内面を考察させる導線が敷かれている。
ミンター氏の異形の作風はどこから来たのか?
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/012.jpg) |
それではミンター氏のクリエイティビティとは何か? ミンター氏は,長髪に髭をたくわえ,羊たちと共に暮らしながらサイケデリックなビデオゲームを作り続けている人物,というマスイメージが確立されている。
僕もその姿から,つい「コンピューター文化と密接に関わっているヒッピー文化を体現するような人ではないか」と勘違いしていたのだが,「LTJMS」はそんなマス・イメージを強調するような内容ではない。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/001.jpg) |
ミンター氏は1984〜1985年に「Mama Llama」や「Ancipital」など,ミュータント化したラクダが頭部から弾丸を放ちカピバラと戦う異色のゲームを作り,プレイヤーを熱狂させたり困惑させたりしてきた。辻褄の合わない奇妙な夢のような世界を次々と作り出してしまうことから,ミンター氏が若い時からヒッピー文化に浸かっていたと想像できるが,「LTJMS」の年表を見るとそうでもないらしい。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/006.jpg) |
もともとミンター氏がゲーム開発を始めたきっかけ自体は,ありふれた理由だ。1970年代末,10代の頃に学校で友達がコモドールのPET 2001でゲームを遊んでいたのを見てBASICのプログラミングを覚えた,というもので,日本でも昔のゲームクリエイターの逸話で聞く話である。
その後ミンター氏はいくつかゲームを生み出すものの,大学時代には心膜炎にかかり,「もしかしたらこのまま死ぬのかもしれない……」と思い悩んだ時期もあった。その療養中に,ミンター氏の心を癒したのがプログラミングだったという。そして心膜炎を乗り越え,地元の仲間との協力によって本格的にゲームクリエイターの道へと進んでゆく。
ミンター氏のサイケデリックな作風とは裏腹に,オフィシャルな経歴の初期は(平たく言ってしまえば)あの時代のクリエイターにしばしば見られたタイプでもある。あまりにも特殊な経歴からビデオゲーム業界に来たというような要素は皆無なのだ。
「LTJMS」ではこうした経歴を踏まえ,随所で編集側が「どこからあの作風が生まれたのだろうか」と考察している部分がある。たとえばミンター氏がLlamasoftを創業した街である,タッドリーの街の環境が作風を作ったのではないか,との考察がある。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/011.jpg) |
タッドリーの街はイギリスの伝統的な,落ち着いた町だという。ところがこの街の隣には,金網で区切られた核兵器研究機関があり,そこではミンター氏の父親が従業員として働いていた。
ミンター氏自身も「たとえ夜中でも,私たちの町がすっかり静まることはありませんでした」「夜中,ベッドに横になると,反応炉を守る臨海警報のカチカチという音が聞こえました」と振り返っている。一方で,従業員の子供は施設の敷地内に入り,アーケードゲームを遊べたらしく,それがミンター氏の原体験になっていると思われる。
「LTJMS」ではミンター氏が静かなタッドリーの町と対照的な核施設で過ごしたことが,ヤギやラクダが宇宙戦争に向かう異常なゲームを作らせたのではないか,と考えられている。だが確証はない。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/004.jpg) |
本作にはミンター氏自身の言葉や,ドキュメンタリー映像での発言も豊富に用意されているのだが,意外にもそこまでアヴァンギャルドな発言はない。
自分のゲームの売り上げの7割をディストリビューターに取られるという法外な状況を,母親に「それはおかしいだろ」と指摘されて目を覚ました,などという世間知らずだった頃の話から,「自分のゲームは開発で大事なのは,フィードバックの繰り返しなんだ」という具体的なゲーム開発の手法についての話まで,ゲームクリエイターには身近なエピソードが多い。
むしろミンター氏のインタビューにおいては,一人のゲームクリエイターから見た,激動の1980年代〜90年代初頭までのゲーム業界でどう生き延びてきたかという生々しい話が興味深い。
ホームコンピュータの時代からパーソナルコンピュータ,そしてコンソールなどプラットフォームが入り乱れ,やがて産業として発展する状況で,80年代初頭のように独立したクリエイターとして作り続けることに苦労した……という話が印象的であった。
一方で,彼自身のインスピレーションの源については,本人の口から深く言及されることはない。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/016.jpg) |
むしろ,周囲の関係者がミンター氏の作品から,ミンター氏を考察せざるを得なくなっている現象自体が興味深い。同じゲーム開発者から元ゲームライター,作家などの関係者もまた,ミンター氏のクリエイティビティがどこから来たのかについて考えあぐねているわけだ。
本作が“最後のインディーゲーム作家”とミンター氏を評するのは,端的に大企業に所属したクリエイターではなく,自分のブランドで活動し続けた経歴を評してのものだろう。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/010.jpg) |
「LTJMS」をプレイする限り,ミンター氏自身は意識して奇をてらっているわけではなく,淡々と新作を開発し,そのたびに周囲が驚いているようだ。その作品群に,ビデオゲームから逸脱したソフトが含まれていることが,ミンター氏への解釈を複雑にする。
年表を追っていくと,コンソールにて普通のビデオゲームとはまったく趣の違う,「光シンセサイザー」がコンセプトのソフト「Psychedelia」を1984年に開発している。
「Psychedelia」とは,ビジュアルエフェクトが煌めく映像を作れるソフトである。音楽のライブでのビジュアル演出に使うVJ(ビジュアルジョッキー)のような映像表現を先行しているソフトと言えるかもしれない。少なくともなんらかのルールに乗っ取ってゲームを攻略するものではない。
ミンター氏は奇抜な世界観とはいえ,ゲームデザイン自体はシューティングやアクションなどのルールが明確なビデオゲーム開発を行っている。一切のルールが存在しない光シンセサイザーのソフトは特異とも言えるが,これもまた彼の作家性に大きく関係している。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/013.jpg) |
「LTJMS」の最後は,1994年にリリースした「Tempest 2000」の紹介で一旦締めることになる。本作はもともとデイブ・ソラー氏が1980年に開発したアーケードゲーム「Tempest」を,ミンター氏がリメイクしたゲームで,コンソール史上,記録的な失敗をしたAtari Jaguarに供給されたソフトだ。
宇宙空間なのか,はたまた人間の無意識下にあるインタースペースなのか,原色のワイヤーフレームで構成された3D空間でのシューティングである「Tempest 2000」は,ミンター氏のビデオゲームデザインと,彼が長らく求めていたサイケデリックな視覚体験の両者が混ざり合い,氏の作家性におけるひとつの到達点となった作品と言えるだろう。
プレイヤー自身が「作家性とは何か」を探る自由
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/007.jpg) |
ドキュメンタリー映画やノンフィクションであれば,何らかの論旨に則って本人や関係者のインタビューが進むものだ。ところが「LTJMS」の場合,ミンター氏の実像自体はどこかミステリアスなまま終わる。すでに英語圏のいくつかのレビューではその点が批判されているが,僕はむしろビデオゲームならではの大回顧展の特性を生かしたものだと評価したい。
大回顧展は,さまざまな展示を通して鑑賞者が自由に「この作家は何者なのだろうか」と考察していくものでもある。そしてビデオゲームが,プレイヤー自身のゲームプレイによって自分だけの体験を作り上げるものだとすれば,「LTJMS」とは,「ジェフ・ミンターの作家性とは何か」をプレイヤー自身が残された作品や発言から自由に考察できる余白が大きいと捉えられる。
なにより,「LTJMS」の最後のドキュメンタリー映像で,これまでキャリアやゲーム開発の具体的な話しかしていなかったミンター氏がぼそっとこう言うのだ。その静かな一言は,ミンター氏の無意識的なクリエイティビティがどこから生まれたかの大きなヒントのように思えた。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / [レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/014.jpg) |
“13歳か,それよりも若かったころ,横になって音楽を聴いていたら,頭の中で音楽に合わせて抽象的な幾何学図形が何かしているのを想像していたのを覚えています。14歳くらいの頃,私は国語の授業中に座って白昼夢に陥っていました。みんなはロックスターになってステージでギターを弾くことを夢見ます。私は何かをやる空想をしていましたが,何なのかは分かりませんでした。大きなスクリーンがあり,そこで色々なことが起きたり,証明が見えたり,ただの創造の一部としてそこにあったのです”
葛西 祝
ジャンル複合ライティング。ビデオゲームを中核に,映画や美術,文学などを越境するテキストを手掛けている。
X:EAbase887
公式サイト:http://site-1400789-9271-5372.strikingly.com/
「Llamasoft The Jeff Minter Story」公式サイト
- 関連タイトル:
 Llamasoft: The Jeff Minter Story
Llamasoft: The Jeff Minter Story
- 関連タイトル:
 Llamasoft: The Jeff Minter Story
Llamasoft: The Jeff Minter Story
- 関連タイトル:
 Llamasoft: The Jeff Minter Story
Llamasoft: The Jeff Minter Story
- 関連タイトル:
 Llamasoft:ジェフ・ミンター・ストーリー
Llamasoft:ジェフ・ミンター・ストーリー
- 関連タイトル:
 Llamasoft: The Jeff Minter Story
Llamasoft: The Jeff Minter Story
- 関連タイトル:
 Llamasoft: The Jeff Minter Story
Llamasoft: The Jeff Minter Story
- この記事のURL:
キーワード
- ゲーム集
- Digital Eclipse
- Digital Eclipse
- プレイ人数:1人
- 企画記事
- レビュー
- ライター:葛西 祝
- PC:Llamasoft: The Jeff Minter Story
- PC
- PS5:Llamasoft: The Jeff Minter Story
- PS5
- Xbox Series X|S:Llamasoft: The Jeff Minter Story
- Xbox Series X|S
- Nintendo Switch:Llamasoft:ジェフ・ミンター・ストーリー
- Nintendo Switch
- :Llamasoft: The Jeff Minter Story
- Xbox One:Llamasoft: The Jeff Minter Story
- Xbox One
(C)2023 DIGITAL ECLIPSE ENTERTAINMENT PARTNERS, CO. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2023 DIGITAL ECLIPSE ENTERTAINMENT PARTNERS, CO. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2023 DIGITAL ECLIPSE ENTERTAINMENT PARTNERS, CO. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2023 DIGITAL ECLIPSE ENTERTAINMENT PARTNERS, CO. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2023 DIGITAL ECLIPSE ENTERTAINMENT PARTNERS, CO. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2023 DIGITAL ECLIPSE ENTERTAINMENT PARTNERS, CO. ALL RIGHTS RESERVED.



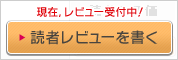
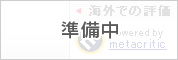



![[レビュー]「Llamasoft The Jeff Minter Story」は “最後のインディーゲーム作家” ジェフ・ミンターの謎を探る,答えのない旅である](/games/808/G080898/20240611046/TN/017.jpg)








