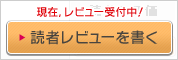イベント
IDC2023「絶対に勝つためのインディープロデューサーの必殺技」をレポート。3名のプロデューサーが自身のプロデュース術を語った
 |
「グノーシア」の川勝 徹氏,「メグとばけもの」のDaigo氏,「NEEDY GIRL OVERDOSE」のさいとーだいち氏が登壇し,企画,開発,販売の各フェイズにおけるプロデュース術が対談形式で語られた。
インディーゲーム最前線に立つプロデューサーたちが,自身のプロデュース術を語る
対談は,「企画フェイズでこれは売れる! という作品はどんなものか」というテーマでスタートした。開発前に企画を精査する段階において,3名のプロデューサー各々がどういった基準で“売れる”ジャッジを下しているかということだ。
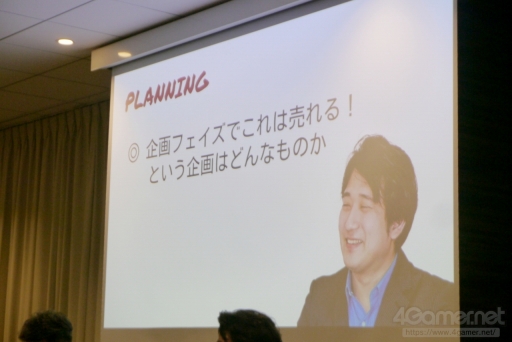 |
Daigo氏の場合「最初に出てきた絵面(イメージボード)がエモいもの」で,自分が感動できるかどうかを優先しているという。「自分は開発者に近いタイプ」と自己分析する氏は,自分が作ったゲームで感動できたときや,シナリオとゲームデザインが絶妙に絡み合ったと思える瞬間を迎えたとき,ヒットを確信するそうだ。これは作品によってタイミングは異なり,「メグとばけもの」の場合イメージボードの段階で,「くまのレストラン」ではもう少し後だったとのこと。
もちろん感覚的なものにのみ頼っているわけではなく,同時に市場調査も行っている。例として挙げられたそれらの作品で言えば,「UNDERTALE」を終えたプレイヤーたちが“UNDERTALEロス”の状態になっていること。同系ゲームを探している人がいるということを知っており,デザインをする際には同作を強く意識していたそうだ。
川勝氏は「グノーシア」について,“一人用人狼ゲーム”という,キャッチーに伝わりやすい部分をもっていたことがそれにあたると話す。ゲームには多層的な魅力があり,いろいろな“良さ”を語りたくはなるものの,ひと言で伝わるような特徴がないと人の気持ちを掴むのは難しい。それは発売後の口コミも同様で,簡単に語れるものがないと拡散は望めない。
これについて川勝氏は,「ユーザーのペルソナ(顧客像)を,どこまで具体的に考えられるかが重要」と話す。「グノーシア」の場合,“プレイヤーの生活の一部に溶けこむこと”を想定し,人狼ゲームの不満点を徹底的に潰したと説明した。
また,「作ったゲームは自分でも購入するし,買いたくないと思うゲームを作ってはお客さんに失礼」と,企画が売れるものになるかどうかは,“自分で作ったゲームを自分で買いたくなるか”が基準になるとも話した。
さいとーだいち氏は,「その人,そのチームでなければ作れないものになっているか」という基準を持っているという。「NEEDY GIRL OVERDOSE」の場合,インターネット文化に精通したにゃるら氏が「インターネットにまつわるゲームを作りたい」と希望した時点でヒットを確信したとのこと。こうした“正統性”を持ったものがインディーゲームではないかと語った。
 |
ユーザーの好みや市場のトレンドを気にせず,自分が作りたいものを優先できるのがインディーゲームの良さ。プロデューサーという立場にある3名は,そういったゲームの企画を提案されたとき,何を重視して採用・不採用を判断するのか。Daigo氏の場合,これもやはり「エモいかどうか」なのだが,しかしそれだけではなく「売れなければ意味がない」という考えも持っているという。
川勝氏は,プロデューサーとディレクターを両方務めた経験を踏まえ,ゲームの企画には「安心要素」と「挑戦要素」が存在すると語る。挑戦するのは大事だが,斬新すぎるゲームは顧客が恐がりなかなか購入してもらえない。開発が自分たちの作品に没頭しすぎると“味が濃すぎて,(そのままでは)飲めない原液のジュース”になりかねないと指摘する。
これを防ぐには,そのジャンルを好きでない人をメンバーに入れ,どういった部分を除くべきか探るのが良いという。「グノーシア」の場合,開発スタッフたちは当初「疑う」と「かばう」というたった2つのコマンドで人狼ゲームを構成しようとしていた。しかし,人狼ゲーム自体があまり得意ではない人の視点でチェックしたことにより,客観的な視点でさまざまなコマンドを駆使する現在の形になったそうだ。
 |
「安心要素」と「挑戦要素」について,さらに詳しく説明された。たとえばRPGであれば,「コマンドRPGだが,武器は1つだけ,街は1つだけ,仲間は3人だけ。それでも100時間遊べる」といったコンセプトであれば,興味の有無は別として,1回見てみたくなるのではないか。川勝氏はそう聴講者に問いかける。
その理由は,知っているもの(コマンドRPGという安心要素)によってある程度イメージできるゲームの仕組みにより遊びを担保し,そこに知らないもの(ここでは,武器や仲間が少ないのに100時間遊べるゲームという挑戦要素)が入っているからだ。このように,安心要素に2〜3割の挑戦要素という新しさを入れることによって,顧客は安心してゲーム開発者の挑戦を受け止めてくれるわけである。
さいとーだいち氏が企画にGoサインを出すか否かの判断をする場合,作品のジャンルに基づく市場調査も行っているという。プレイヤー人口の関係上,売上上限が見えてくるジャンルも存在するが,こうしたジャンルの開発を打診された場合でも,開発者に“正統性”があり,良いものになるという確信があるのであれば,上限のことを伝えたうえで開発を進めていくのだという。
氏がプロデュースした「DRAINUS」は良い例だが,Team Ladybugが作るのであれば良いゲームになることは分かっているので制作を進めたのだそうだ。
 |
登壇者3名はそもそも,どういった経緯でプロデューサーという役割を担うことになったのか。さいとーだいち氏は「プロデューサーが最初からいるわけではなく『開発の仲間から分岐するもの』『売る係』であり,やりたくてやっているわけではない」と語る。
これまで無関係だった人間がいきなりプロデューサーをやるといっても信用を得るのは難しく,それゆえに仲間の中で向いている人,売りたい人が「仕方ねえな」でやるもの。大変な仕事であるため,仲間たちへの愛情があり「こいつらのためなら(プロデューサーを)やってもいい」というケースが多いのではないかとのことだった。
川勝氏は,自分がプロデュースするゲームの開発チームは「バンドのようなもの」であると話した。そもそも開発チームは,ゲームを作るため集まったのではなく,もともとは麻雀でをするために集まった仲間。リーマン・ショックの影響で仕事が減ったことから,なんとか生計を立てたいということでゲーム開発をスタートした仲間たちだったそうだ。
川勝氏曰く,仲間たちは「頭は良いが,生き方は弱い(処世術に長けていない)。才能はあるが,なかなか人生は上手くいかないかもしれない。だからせっかく生み出したものをもっと世に広めて知ってもらいたい人々」だという。だからこそプロデューサーとして頑張れて,自分が難しい仕事を引き受けることで信頼関係を築けると話した。
また,プロデューサーとして自作をアピールするうえでは,Indie Developers Conference 2023のように業界関係者が集まるチャンスを捉えて,同業者やメディア関係者とコミュニケーションを取り,イベントの後でコミュニティに参加できるかどうかが大事だという。コミュニティでは濃密な話がされており,氏の経験上,日本のインディーゲーム界で成功している人は大体がどこかのコミュニティに所属しているのだそうだ。
さいとーだいち氏は,「コミュニティなくして作品は生まれてこない」と指摘。Daigo氏も,さまざまな縁があって有能なスタッフが集まって作品を作っているが,プロジェクトが失敗したときのスタッフは,商用ゲームを完成させた経験が無い人であることが多かったという。
 |
続いて,制作フェイズにおいて“どう作るか”が語られた。
川勝氏は,リーダーに必要な資質として「絶対的な安心感と,環境作りの能力」を挙げた。とはいえ,川勝氏もこうした資質を最初から持っていたわけではなく「やらないといけなかったから」であると自身の経験を語った。
また,制作フェイズであっても,イベントには定期的に出展したほうが良いとも話す。繰り返し顔を出すことでコミュニティが作られ,会場で得られたプレイヤーの声を開発側に伝えれば,プロデューサーと開発の人間関係を円満に保ちつつ,改善すべき点を直せるという効果もあるという。
川勝氏は,制作フェイズの注意点として,貯金(資金)が減って心に余裕がない状態での判断は非常に危険とも話した。制作を進めるうえで,リーダーはさまざまな判断を下さなければならないが,こうした状況に陥った場合,変な作り方や見切り発車をしてしまう可能性があるそうだ。
川勝氏はそうした状況について,「開発を継続するのではなく,資金をチャージして心の余裕を取り戻してほしい」とアドバイスした。外部からの出資を受けている場合はそうもいかない点は注意が必要だと川勝氏は語る。
「辛く,苦しく,分からなくて,つねに考えるしかないのが制作」と話すさいとーだいち氏も,川勝氏が話す資金繰りの注意点に同意する。氏は,そういったプレッシャーを自分のところに留めておくのもプロデューサーの役割と考えており,そういった心労から体重が7kg減ったこともあるそうだが,「プロデューサーは苦しむのが仕事」とも語っていた。
一人で下さなければならないこの判断において,最終的に頼りになるのは企画フェイズでの確信であるという。こうしたスタンスが効を奏してか,氏はプロジェクトをキャンセルする決断を下したことがないのだそうだ。
 |
Daigo氏は,開発者としての立場から「企画のフェイズが終わっていないのに,制作フェイズに入ってしまう人が多い」と指摘する。プロトタイプではなく本制作に入ってしまうのは,作品のコンセプトが決まっていないことと同義であり,二転三転した挙げ句に完成しないことが非常に多いのだという。
そして制作フェイズは「唯一コストをコントロールできる部分」であり,氏の「くまのレストラン」「メグとばけもの」では同じゲームエンジンを使い,一つのソースコードから全プラットフォームのバージョンを作れるようにするなど,コスト削減に努めているのだそうだ。
作品が完成したら,次は販売戦略のフェイズだ。Daigo氏の場合は「売れなくても死なない会社作り」を心がけつつ,コンスタントにゲームを作る力を追求しているという。
コンスタントにゲームを出し続けることには,運営型でないからこその強みがあるとDaigo氏。買い切り型のゲームは,一度出せば運営型のようにコストを掛けなくても売れ続けることもあり,自身のプロジェクトでは「くまのレストラン」のような小粒で遊びやすいタイトルを積み上げていくことが王道であると感じているそうだ。
川勝氏は,インタビューを受けること,“作者のストーリーそのものを売る”ことの重要さを指摘する。ゲームはプレイしないと分からないもので,その中身の話をしても読まれないが,「グノーシア」で「6000回のテストプレイ」「制作期間4年」というエピソードを強調したように,キャッチーな言葉には人が食いついてくると川勝氏は話す。
インディーゲームを売るうえでは,作者のストーリーに共感を得られるかどうかが重要であり,そのためには自作のどこを切り取って伝えるかを考えた上で,メディアへプレスリリースを送ることを勧めた。
 |
最後に,対談のテーマである「絶対に勝つためのインディープロデューサーの必殺技」について,さいとーだいち氏は「コミュニティと場所を作ること」であると語る。
氏が「殺戮の天使」をプロデュースできたのは,ゲーム実況という場所の魔力があり,そこに乗れればいいゲームは売れるという確信があったからであるという。「インディーゲームは実況してもらわないと売れづらいのも確か」であり,勢いがある実況者複数に実況してもらい,売れていることを認識してもらうことで実際にゲームが売れていくのだという。
一方,Daigo氏は「メグとばけもの」について,実況界隈ではバズったものの,売上にはつながっていないと認識しているとのこと。これについてさいとーだいち氏は,「実況されることでIPとしての伸びはあり,グッズが売れる可能性は増えたのではないか」と,ゲーム単体ではないIPとしての広がりの可能性を語った。
川勝氏は「自分が伝えたいことが実況者に伝わっているかどうかが大事」であると語る。氏のプロデュース術では何を伝えるべきか整理することを重視しているのは前述した通りだが,ゲーム実況ではこれを再確認することも可能というわけで,こうしたフィードバックは今後の作品作りにも役立てられるものではないだろうか。
インディーゲームの最前線で活躍する3名が集まったのに加え,聴講者がいつ質問しても良いというオープンな形式であったため,対談は大きく盛り上がった。開発者向けイベントらしい実践的なアドバイスもあり,現在インディーゲームを開発している人には参考になるはず。個人的にも,第2弾,第3弾を期待したい対談であると感じられた。
 |
- 関連タイトル:
 グノーシア
グノーシア
- 関連タイトル:
 メグとばけもの
メグとばけもの
- 関連タイトル:
 NEEDY GIRL OVERDOSE
NEEDY GIRL OVERDOSE
- この記事のURL:
キーワード
- PLAYISM
- プチデポット
- :グノーシア
- :メグとばけもの
- :NEEDY GIRL OVERDOSE
- WSS playground
- WSS playground
- xemono
- Odencat
- Odencat
- OTHERS
- イベント
- ライター:箭本進一
(C)2021 Petit Depotto. Licensed to and published by Active Gaming Media, Inc.
(C)Why so serious, Inc. All Rights reserved.