イベント
[GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/001.jpg) |
しかしながらそのゲームメカニクスは非常に変わっていて,「原則として死なない主人公」が,マップ上に配置されたさまざまなトラップに引っかかり,四肢を切断されたり焼け焦げたりしながら,そのことを利用して問題を解決する(ちぎれた腕を投げて高所にあるものを落とす,胴体を半分にされることでシーソーのバランスをとる,火だるまになることで暗闇を照らしながら進む)という,なんとも過激な内容となっている。
しかも,そうやって首だけの姿にまでなる主人公はボタン一つで元の姿へと戻るし,謎の巨大な怪物は追いかけてくるし,二足歩行の鹿が不思議な儀式を行うし,主人公が手にしたぬいぐるみは主人公に話しかけてくるしと,とにかく「不思議」としか言いようのない世界が展開される。
このあたり「さすがは『個性的』なゲームを作ることで全世界にその名が轟くSWERY氏の作品だな」と思わせられるし,物語が進むに連れて徐々に見えてくる真相から,さらにその思いを強くする人は多いだろう。実際,本作をプレイしたプレイヤーの多くが,この作品が描くテーマを前に「感動した」「共感した」という感想を語っている。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/002.jpg) |
そんな「とんでもなく変わったゲーム」であると同時に,人々の共感を集めるThe MISSINGがどのようにして作られたのか,GDC 2019で作者であるSWERY氏自身が語った講演の模様をお届けしよう。
なお,この講演はThe MISSINGのネタバレを前提としたものなので,「まっさらな状態で『The MISSING』を遊びたい」と思う方はここで一度引き返し,クリア後に続きを読んでいただきたい。もうクリアした,ないしネタバレどんとこい,という方のみ,ここから先に進んでほしい。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/003.jpg) |
「ゲームプレイとシナリオが融合するゲーム」を目指して
The MISSINGというゲームは,主人公J.J.が「追憶島という美しい島に親友と二人で遊びに来たが,夜が明けると親友は姿を消していた。探しださねばならない」というところからスタートする。そしてゲームが始まってすぐに謎の雷に打たれたJ.J.は不死の能力を授かり,その能力を駆使して親友の探索を続ける。そうやって旅を続ける中で,J.J.のスマホにある家族や友人とのチャットログが明かされていき,人間関係の中で感じている苦悩が透けて見えるようになる。
ゲームが後半に入ると,J.J.は追憶島に存在しないはずの,思い出の時計塔に入る。そこでこの追憶島は死後の世界であり,プレイヤーはJ.J.が自殺しようとしたのだということに気づく。このゲームはまさにJ.J.の臨死と心の痛みの体験だったというわけだ。エンディングを迎えたプレイヤーは,この物語が親友を探す物語ではなく,自身が再生するために己自身を見つけ直すという,苦痛と再生の物語であったということを知る。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/004.jpg) |
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/005.jpg) |
……というのが,講演で明かされたThe MISSINGの概要である。
しかしながら本作には,登場人物たちが互いにセリフを投げかけ合う長尺のイベントシーンやムービーシーンはほぼ存在しない(まったくないわけではないが,「テキストチャットする」のが基本だ)。にも関わらず,プレイヤーはこの複雑な物語を,実際のゲームプレイから感じ取れる。
この背景には,SWERY氏が「ゲームプレイとシナリオが融合するようにしてゲームをデザインしたから」という背景がある。ではいったい,どうやってそんなことを可能としたのだろうか?
「The MISSING」には2つの苦痛と再生が組み込まれている。
ゲームシステム側で言えば,それは,「肉体の痛み」と「それが無限に再生する」という能力。物語においては,徐々に明らかになっていく心の痛みと,それを打ち破るという再生の物語だ。
しかしながらゲームに触れたばかりのプレイヤーは,この双方に触れても,「なんだか変わったパズルだな」としか思わない。しかしゲームを進め,苦痛と再生を繰り返すうちに,プレイヤーもまた苦痛と再生を体験し,共有できるように作られている。
「自己欠損を行うゲームプレイと,それが主人公の臨死体験中の心の痛みということがシンクロしていることで,エンディングを迎えたとき,プレイヤーがこの矛盾を抱えた行為そのものを受け入れられるようになる,という構造になっている」(SWERY氏)というわけだ。
そしてこの構造を作るにあたって,SWERY氏は意外な制作手法を採用している。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/006.jpg) |
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/007.jpg) |
ゲームシステムが先,という制作工程
SWERY氏はまず「ゲームのストーリーは,ゲーム体験と強く結びついているほど,プレイヤーに与える感動は大きいのではないか」という仮説を立てた(そしてこれは小説や映画では得られない感動でもある)。
この仮説を立証するため,SWERY氏はThe MISSINGの開発において「先にシナリオを作らない」ことにした。「お話のためにステージを作る」のではなく,「ゲームの上にお話を載せる」という方向性だ。
これにあわせて,後からシナリオを書いても話がつながるように,ステージのロケーションは「どんな順番でプレイしても大丈夫」なように設定されている(森・滝・産業廃棄物処理場・ダイナーといったステージは,どんな順番で接続されていても問題がない)。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/008.jpg) |
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/009.jpg) |
続いて,ゲームシステムと物語の主人公がどんな関係になっているかが解説された。
「苦痛と再生をゲームとしてプレイヤーに体験させるため,最初に取り組むべきはゲームシステムと強く結合したプレイヤーだ」と語るSWERY氏は,それと同時に「ではなぜ本作の主人公はアンデッドやダークヒーローではなく,少女なのか」と聴衆に問いかけた。その理由は「プレイヤーに何を体験させたいかによって,主人公が変わってくる」からだという。
例えば銃を撃って敵を倒すゲームを想定しよう。
このときプレイヤーに「爽快感や無双感を味わわせたい」ならば,適合するストーリーは「押し寄せる大量のゾンビを撃ち殺す」ことになり,従って主人公は「元特殊部隊員のコック」といったものになる。
もしプレイヤーに「義務感や任務を遂行する感覚を味わわせたい」ならば,適合するストーリーは「愛する者を守るために戦場に向かう」ことになり,従って主人公は「家族思いの兵士」ということになる。
あるいはプレイヤーに「切迫感や現実感を味わわせたい」ならば,適合するストーリーは「生き延びるために食料を探す」ことになり,従って主人公は「年老いたベテラン猟師」ということになる。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/010.jpg) |
The MISSINGは「自己破壊と再生を利用したパズル」のゲームであり,プレイヤーに「苦痛と救済を味わわせたい」ので,適合するストーリーは「誰か大事な人を探しながら,暗闇の深奥で迷う」,そして主人公は「等身大の若者」ということになる。
この登場人物設定と物語は,ゲームシステムにもフィードバックされる。自己破壊するときのアニメーションや再生するときの苦痛のモーション,キャラクターの移動速度やステージの色調といったものは,物語とキャラクターが定まったからこそ決定できるものだ。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/011.jpg) |
若者が共感し,感動できるゲームを作る
もうひとつ重要な技術として,どうやって物語に共感させるのかという問題がある。
これについてSWERY氏はまず「物語の導入はできる限りシンプルにすべきだ」「不思議なシーンを描くのであれば,それは演出(美しい星空が急に嵐に変わるといった,ステージの構造に影響を与えないもの)で行うべきだ」と語った。
これはThe MISSINGがプラットフォーマーであるところにも通じており,「プラットフォーマーであれば,プレイヤーはとにかく右に進めば話が進むことを知っている」というメリットがある。従ってゲームの側から進行方向を指示したり,テキストを提供したりする必要がない(それだけプレイヤーはゲームに集中できる)。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/012.jpg) |
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/013.jpg) |
その上でSWERY氏が「最大の発明」と語ったのが,スマートフォンでのチャットを使ったキャラクター描写だ。
The MISSINGにおいては,ぬいぐるみとのチャットを除けば,ゲーム中で明かされていくチャットログは文字通りすべて「J.J.の過去」を浮き彫りにしている。J.J.がどんな性格で,周囲の人々とどんな関係性を構築しているのかが,そのログからにじみ出てくるのだ。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/014.jpg) |
また,SWERY氏は「この作品を,若い人にも感動してもらえるものにしたい」と考えていた。
このため若いプレイヤーが共感できる物語とするため,主人公の悩みは等身大かつ個人的なものとなっている(世界を救う必要はない)。文字で物語が提供されるフォーマットが,若い人にとって最も一般的な「スマートフォン上でのチャット」になっているのも,狙いは同じだ。
徹底的なヒアリングに基づき,現代の若者は自己実現欲求・承認欲求を満たされない環境にあるということに気づいたSWERY氏は,その点も物語のテーマに加えてもいる。さらに「オッサンには書けない,青さのようなものを描く」ために,セカンドライターとして大学院生を起用した。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/015.jpg) |
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/016.jpg) |
「記号」は,キャラクターの個性ではない
続いて,魅力的な主人公をどうやって作るかという点が解説された。
「彼女のキャラクターを愛してもらうためには,憧れと共感が不可欠」と考えたSWERY氏は,この2つを実現するため,「他人から見られた自分」と「内面的に感じている自分」の両方を描くのが一番良いと考えた。
このうち「憧れ」は超常的な再生能力であったり,「親友を追う」という行動を通じて表現できる。だが「共感」となると難しい。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/017.jpg) |
さまざまな可能性を考えた末,SWERY氏は「性別・人種・言語・思想を越えて共感を得るためには,『偏見』というものと向き合う必要がある」と感じたという。
SWERY氏は「僕は,すべての人は何らかの形でマジョリティであり,何らかの形でマイノリティだと考えている。例えばこのGDCの場において日本人である僕はマイノリティだが,日本に帰れば圧倒的マジョリティになるように」と語る。こういった「人はマジョリティであり,かつマイノリティでもある」という現実に,エンディングを迎えたプレイヤー自身が気づいてくれたらよいなという思いに基づき,The MISSINGのストーリーは作られた。
下にある2枚のスライドは,The MISSINGにおける迫害と共感のフローだ。ゲーム開始時においては主人公=人間=マジョリティという感覚でスタートするが,奇怪な事件や怪物,不思議な生物と遭遇するなか,徐々にこの世界において自分はマイノリティであることに気づく。そして物語の終盤に入ると,主人公は自分がマイノリティであることを苦にして命を断ったことが分かり,プレイヤーもそのことに苦痛を感じる。
エンディングで主人公はそれらすべてに打ち勝ち,プレイヤーはその姿に自分を重ねることで,「これは自分の物語だ」と感じられるようになる。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/018.jpg) |
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/019.jpg) |
ちなみに質疑応答では「J.J.というキャラクターがマイノリティであるという部分に自分を重ねられなかったとしても,誰かにいじめられたり,あるいは自分がいじめる側に加担したりといった経験は多くの人が共有しているのだから,その面からプレイヤーはJ.J.の物語を自分の物語として感じ取れるはずだ」とSWERY氏は語っている。
なおSWERY氏は「J.J.というキャラクターを通じて発見し,言語化できたこと」として,キャラクターを構成する記号は,キャラクターの個性ではないという点を指摘した。
ゲームに限らず,キャラクターはしばしば性別や国籍,出身文化といったものを特性(記号)として有する。けれどそれらは個性ではないし,「それらを個性と勘違いしてはならない」(SWERY氏)。
「大切なのはその人自身の個性であり,表現すべきはその人の唯一無二の部分」であって,「一人の人間としての性格や思想のほうが,ステータスよりも重要」かつ「それがキャラクターの魅力となる」というわけだ。
またSWERY氏は,キャラクターを定義する「履歴書」として,The MISSINGでは以下のような項目を設定した。
(1)これまでの人生
(2)趣味趣向・技能
(3)興味の対象とその熟練度
(4)両親や友人,近親者の環境
(5)近親者からの客観的評価
(6)表面的な知人と,彼らからの客観的な評価
(7)本人の自己評価
※これはシミュレーションや学術的に利用できるものではなく,ストーリー上これらが必要になる,という定義である
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/020.jpg) |
The MISSINGでは特に(5)(6)に力を入れて作られている。
が,実のところ主人公を取り囲む人物のうち,3Dモデルがあるのはエミリーだけだ。それ以外の人物は,ビジュアル的にはせいぜいがチャットのアイコン表示を越えない。
だが彼らは物語における「過去」として登場してくるため,どの人物も「人格に対して完全に自由」(SWERY氏)という特徴がある。つまり物語の要請によって特定の会話を強いられることなく,ただ個々人の個性に基づいた発言しかしないのだ。これはチャットログがゲームのストーリー展開に依存しない形で提供されればこそ,可能となった表現と言える。
これらすべてを踏まえ,SWERY氏は「壁を越えるキャラクターは極めて重要」と指摘する(The MISSINGにおいては,ぬいぐるみのF.K.がこれに相当する)。
「自由に壁のあちらとこちらを移動できるキャラクターがいないと,物語はただの議事録で終わってしまう」し,「壁越えをどれくらい強引かつスマートにできるかが,ストーリーの妙味となる」というわけだ。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/021.jpg) |
「お前がやるべきことをしろ」
講演の最後にSWERY氏は「最も重要だったこと」として,The MISSINGのスタート時に表示される「この作品は,すべての人々が自分自身であることを否定しなくても良いという信念のもとに作られています」というメッセージのことが語られた。
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/022.jpg) |
このメッセージが示す内容自体は,開発の間じゅうずっとチームの内部で共有されていたという。けれどこの文面としてゲーム内部に,しかも冒頭部分に実装されたのは,開発の大詰めに入ってからだったという。
「『この作品は複数の宗教人種ジェンダーからなるチームで作っています』みたいなメッセージを入れていたけれど,今思うとかっこ悪いし,言い訳にしか見えなかった」(SWERY氏)ものに対し,アドバイザーから「SWERYが言いたいことってこういうことだよね?」というズバリの言葉が寄せられたことで,「この言葉をそのまま表示しよう」と決意したという。
だが問題は,その決定のタイミングだった。開発の大詰めというのは言葉のアヤで,実際にはバグチェックもほぼすべて終わりかけた「事実上完成」状態での変更だったのだ。当然ながら「プログラマーは怒り,プロデューサーは鼻血を出した」(SWERY氏)が,それでもこの一文はゲーム開始時に挿入されることになった。
この顛末についてSWERY氏は,「開発スケジュールの奴隷になるな。『お前がやるべきことをしろ』」と語る。確かに,スケジュールを何よりも重視すれば,作品は期日通りに発売されるだろう。けれどそれでは「投じた情熱と努力がすべて無駄になる可能性がある」(SWERY氏)のだ。
無論,筆者ももしプログラマやプロデューサーの立場で「今からこれを足す」と言われたら,そんなことを言い出した輩を一発ぶん殴ってやろうかと思うくらいには怒るだろう。それでもなお,「お前がやるべきことをする」必要があるならば,しなくてはならない。そして事実,The MISSINGは根強いファンを獲得し,講演の後は別室に移動して質疑応答の延長と記念撮影が行われていた。
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / [GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/023.jpg) |
講演が示すように,一見すると奇抜に見えるSWERY氏の作品は,しっかりとした理詰めで作られている。それは間違いなく,氏の作品の魅力のひとつだ。
けれど,作品に対する強い覚悟と,それが最終的にチーム全員にとってプラスになるという判断力。これもまた,SWERY氏が世に問う作品を支えている要素なのではないか――そんなことを感じさせられる講演だった。
「The MISSING - J.J.マクフィールドと追憶島 -」公式サイト
4GamerのGDC 2019関連記事
- 関連タイトル:
 The MISSING - J.J.マクフィールドと追憶島 -
The MISSING - J.J.マクフィールドと追憶島 -
- 関連タイトル:
 The MISSING - J.J.マクフィールドと追憶島 -
The MISSING - J.J.マクフィールドと追憶島 -
- 関連タイトル:
 The MISSING - J.J.マクフィールドと追憶島 -
The MISSING - J.J.マクフィールドと追憶島 -
- 関連タイトル:
 The MISSING - J.J.マクフィールドと追憶島 -
The MISSING - J.J.マクフィールドと追憶島 -
- この記事のURL:
キーワード
- PC:The MISSING - J.J.マクフィールドと追憶島 -
- PC
- アクション
- アドベンチャー
- White Owls
- アークシステムワークス
- PS4:The MISSING - J.J.マクフィールドと追憶島 -
- PS4
- Nintendo Switch:The MISSING - J.J.マクフィールドと追憶島 -
- Nintendo Switch
- Xbox One:The MISSING - J.J.マクフィールドと追憶島 -
- Xbox One
- イベント
- ライター:徳岡正肇
- GDC 2019
- Game Developers Conference
(C) White Owls Inc. / ARC SYSTEM WORKS
(C) White Owls Inc. / ARC SYSTEM WORKS
(C) White Owls Inc. / ARC SYSTEM WORKS
(C) White Owls Inc. / ARC SYSTEM WORKS


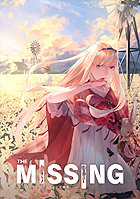
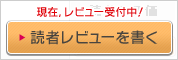
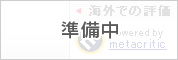





![[GDC 2019]己の身体を破壊し,再生させながら進むパズルプラットフォーマー「The Missing」が目指したものをSWERY氏が語る](/games/410/G041023/20190323024/TN/024.jpg)






