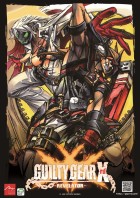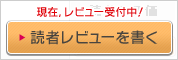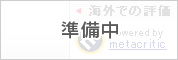インタビュー
今を代表するバトルプランナー陣が語る,格闘ゲームの作り方。アークシステムワークス×フランスパン合同座談会
コミュニティとバトルバランスにまつわる都市伝説
4Gamer:
ここからは,格闘ゲームにまつわる都市伝説……というか,さまざまな噂話を一つ一つ検証してみたいと思います。まず最初は,「追加キャラやDLCキャラって,意図的に強くしてない?」という質問です。これはどうなんでしょうか?
鴨音氏:
開発側としては,既存キャラクターの研究が進んでいる中,後発で登場するキャラクターなのだから,ある程度使いやすいほうがいいよね,とは考えます。でも“DLCだから強くしよう”ってことはありえないですね。
パチ氏:
既存のプレイヤーから注目してもらえる,楽しんでもらえる特徴を作らなくちゃならないから尖ったキャラクターになりがち,というのはあるかもしれない。その結果,蓋を開けてみたらそのコンセプト自体が強かった,ということはありえます。
例えば,さんざん強すぎると言われた(BBCPの)ココノエだったら,あれは重力場を設置して自分の攻撃や相手を引き寄せられるというのがコンセプト。それによってどれだけ面白い遊びが作れるのか,というのが我々のテーマで……まあ,仕様を切ったのはこの人(マスクマン1号氏)なんだけど(笑)。
マスクマン1号氏:
ええと,「面白いから良いじゃん」という感想を心の支えにして生きています(苦笑)。
パチ氏:
実際,あれは面白いと思うんだよね。で,そこからセットプレイが開発されてどうこうっていうのは,プレイヤー達の努力の賜物なわけですよ。それが結果的に強くなってしまったという話なんです。
 |
鴨音氏:
そもそも,そういうコンセプトが尖ったキャラクターって,飛びつくのはたいてい元から格闘ゲームがうまい人ですからね。システムを深く理解している上級者は,やっぱり刺激に飢えているので。その結果,研究が一気に進んで強くなるという。
4Gamer:
ああ,それはありそうです。あと,そもそもキャラクターが多すぎるんじゃないかって話もあります。BLAZBLUEシリーズは,次の「CENTRALFICTION」で登場キャラが30の大台に乗るのでこの場では最多になりますが……多すぎないですか?
遠藤氏:
実際,新キャラクターのネタを出すのも大変ですし,チューニングも難しくなっていっているというのが正直なところです。とはいえ,シリーズものですから,よほどの理由がない限りは減らせないんですよね。……キャラクターがいなくなると,今までのプレイヤーさんから,苦情が来ますし(苦笑)。
パチ氏:
もう,メチャクチャ言われるよ(笑)。
4Gamer:
ゲームバランスだけを考えるなら,どれぐらいのキャラ数が妥当なんでしょうか。
遠藤氏:
うちの加藤は,「プレイヤーのことを考えると,バランスは10キャラぐらいが一番取りやすい」って言ってましたね。
鴨音氏:
自分もプレイヤーとしてキャラクター対策をしっかりやるとなったら,やっぱり10キャラぐらいが丁度良いと感じます。UNIは「Exe:Late[st]」で17キャラになりますが,この数になると,対戦ではなかなか出くわさない,いわゆるレアキャラがちょこちょこ出てくる印象です。
パチ氏:
「バーチャファイター4」だって,あれだけプレイヤー人口が多かったのに,レアな印象を受けるキャラがいたからね。あれだって13キャラしかいないのにさ。とはいえ,じゃあ10キャラくらいでいいのかって言うと,今度は少なすぎるって言われるんだよね。
鴨音氏:
BBシリーズはあれだけ1キャラが奥深いのに,よくキャラクターを増やし続けられるなって,いつも驚きですよ。「MELTY BLOOD Actress Again Current Code」は,31キャラ×3スタイルで都合90キャラ近くいましたけど……もうExcelの表とにらめっこする日々でした。
4Gamer:
ただ,BBシリーズはキャラクター固有のシステムが多いので,対策する側も覚えるのが大変じゃないですか? 固有のゲージを持っているキャラも多いですし,その分画面の情報量も増えることになる。
遠藤氏:
固有ゲージがあると,独自の制限を設けることで強力な技を設定できるので,キャラクターの個性を出すのに重宝するんです。ただBBCP以降は,固有のゲージはなるべく増やさないようにしているんですけど。
パチ氏:
そうだっけ。アマネにココノエ,イザヨイと……結構いない?
遠藤氏:
加藤曰く,あくまでも「減らす努力をしている」というだけで,減らすとは言っていない,ということですね(苦笑)。
4Gamer:
分かりました(笑)。では反対に,その結果として生まれたトレンド――このキャラが強すぎる,弱すぎるといったプレイヤーからの意見は,その後の開発にどの程度影響を与えるのでしょうか。現に,先のココノエはその後に弱体化されたわけですけど。
パチ氏:
コミュニティの反応はもちろんチェックしていますし,参考にはしていますが……最終的に調整を決めるのは,バトルプランナー自身がやり込んでみて調べた結果,納得できたかどうかなんですよ。自分が設計した遊び方,引いた導線に対してね。
鴨音氏:
プレイヤーが研究した結果,僕らの想定以上に強いキャラクターが生まれてしまう,ということはありえます。そうなってしまったとき,まず我々が考えるべきは“なぜ自分はそうなることを見抜けなかったのか”ということ。具体的な調整案はその次なんですね。データの取り方が悪かったのか,開発環境やテスト環境に問題があったのか。その辺りを見直すことが大切です。
4Gamer:
プロゲーマーのウメハラさんが「うまい奴が頑張ると,キャラクターが弱体化される」というようなことを言っていましたが(関連記事),そういうことはありえないと?
パチ氏:
自分達のタイトルが稼働/発売した後も,我々はずっと調べ続けていますし,その結果プレイヤーの研究が進む前から「これはちょっとやり過ぎたかな」という要素が見つかることが往々にしてあるんです。調整ではそうした部分にまず手を入れていくので,結果的に「コミュニティからの意見が多かったから調整した」ように見えるかもしれない。でも,例えば特定の誰かが何百連勝したとか,大会で優勝したキャラが弱くなるということは,まずないですね。
鴨音氏:
それは自分も強く言いたいです。結局,強いのはキャラクターじゃなくてプレイヤーなんですから。
パチ氏:
そうそう。コミュニティの反応を見ていると,キャラクターの強弱で語られることが多いけど,勝てるかどうかは結局プレイヤーの力量なんですよ。だから勝っている人は「キャラが強いんじゃなくて,俺が強いんだ」って胸を張って言ってほしい。我々がただ流されて調整することなんて,ありえませんから。
 |
4Gamer:
ちなみに,ロケテストでのアンケートなどはどの程度ゲームに反映されるのでしょうか。ロケテストから大きく変更されることって,今はあまりないような気がしますが。
パチ氏:
これがね……けっこう闇が深いんですよ(苦笑)。
鴨音氏:
ええと,ロケテストでのアンケートの回答には,基本的に全部目を通しています。ただ,乱暴な書き方をする方も多くて(苦笑)。なので,最近は綺麗な文章に整形してもらってから読むようにしたり,心が荒んだときはアニメ見て癒やしたりとかしてます。メンタルケアが大事ですね。
パチ氏:
うちも必ず目は通しますが,「インターネットで見たんですが,この技は強すぎると思います。ロケテスト:不参加」ってお便りが何通もあったりすると……うーんって(苦笑)。人が〜とか皆が〜とかは置いといて,個人の意見をいただけるとありがたいです。いわゆる開発ロケテって,実際に遊んでもらわないと分からない,プレイヤーの感情の動きを見るのが主な目的なので,攻略的な“調べ”よりは,手さぐりの状態でガンガン戦ってみてほしい,というのが本音です。結局,それが一番参考になりますからね。
マスクマン1号氏:
ただ,未プレイの人の意見は参考にしないのかというと,そういうことでもなくて。例えば新システムに関しての印象なんかは,どんなイメージを持たれているのかを,プレイの有無に関わらずチェックしたりしています。悪いイメージだと,本来楽しめるはずの人まで敬遠するようになることもあって,開発側としては無視できない問題なんです。
パチ氏:
ポジティブに考えれば期待の裏返しとも言えるのですが,難しいですね。とくに新システムなんかは,とくに理由もなしに「いいから元に戻せ!」みたいな意見が多くなりがちですし,逆に何も調整していないと,飽きるからもう少し調整してくれって言われちゃうし(笑)。
鴨音氏:
格闘ゲームを好きな人,皆が皆,文才があるわけじゃないですから。結局は,ロケテストの現場を直接見て,雰囲気を感じ取るのが一番かなって思ってますね。
 |
格闘ゲームにおけるバトルデザインのトレンドについて
4Gamer:
ここまでは,主に現在の格闘ゲームについてうかがってきましたが,ここからは未来についても聞いてみたいと思います。格闘ゲームは,今後どんな方向に変わっていくのでしょうか。
マスクマン1号氏:
未来というわけではないですが,今は昔と比べてボタンの数が減り,必殺技が簡単に出せたり,コンボを簡単につなげられたりと,とっつきやすくする方向に進んでいるとは感じますね。
遠藤氏:
やはり,「まずはプレイ人口を広げることが大事」だと思うので。これは加藤の言葉ですけど,BBシリーズにスタイリッシュタイプを用意したのも,まさにそんな理由からです。今まで格闘ゲームを敬遠していた人にも遊んでもらいたいですからね。
マスクマン2号氏:
原作ものであるP4Uシリーズは,そのために作ったようなものですしね。格闘ゲームをプレイしたことのない人に触ってもらいたいなら,やはり「皆さんに向けたゲームですよ」という姿勢をしっかりと見せていくことが大事です。なので,操作の面で取っつきやすくというのは,かなり気を配りました。
4Gamer:
その辺りは,電撃FCにも共通するコンセプトですよね。
鴨音氏:
そうですね。初心者にとっての操作面でのネックは,ほぼレバー操作に集約されるんです。一方で,ボタン操作ではそれほど差は付かない。なので電撃FCでは,必殺技を出すために必要なレバー操作を最小限にし,システム的な行動もできるだけボタンの同時押しに割り振って,かつ4ボタンに収めるようにしました。電撃FCの設計思想は,ほぼここに集約されています。
マスクマン1号氏:
とはいえ,電撃FCはサポートを除けばほとんど3ボタンですよね。P4Uも初心者向けにデザインしたつもりですが,電撃FCを見たときは「ここまでシンプルにしてもいいんだ!」と驚かされました。P4Uも3ボタンにすれば……。
パチ氏:
P4Uや電撃FCは,設計から操作を簡単にする要素が盛り込まれていて,羨ましいよね。GGXrdは5ボタンから変えるわけにはいかないし,操作難度を下げるにも限界がある。後からスタイリッシュタイプも用意しましたが,使うボタンを減らすべきかとか,色々と悩みました。
4Gamer:
P4Uと電撃FCでは,電撃FCの方がリリースは後発になりますが,P4Uを参考にしたところはあったのでしょうか。
鴨音氏:
参考にしていないと言うと嘘になりますが,以前にもお話ししたとおり,インパクトスキルなんかはシューティングゲームのボムが発想の根底にあります。格闘ゲームで実力が出るのは,攻撃よりもむしろ防御ですので,そこを同時押し操作で切り抜けることができれば,ある程度は差を埋められるんじゃなかって。
パチ氏:
初心者向けでこそないですが,そこはギルティギアシリーズのロマンキャンセルや,BBシリーズのオーバードライブにも通じるものがあります。操作難度ではなく「必要な瞬間に押せるかどうか」の判断力が問われる要素になっていて,そこで優劣が生まれてくる。そういった“ボタン操作にフォーカスしたバトルデザイン”が,これからのトレンドと言えるんじゃないかな。
 |
4Gamer:
3D格闘ですが「鉄拳7」のレイジアーツの背景にも,そういった思惑があるのかもしれませんね。ただGGXrdに関して言えば,操作難度をあえて高くしている部分もあるのでは? リバーサルの受付時間が短かったり,押しっぱなし入力では受け身※が取れなかったりとか。
※受け身が可能になる前からボタンを押し続けておくことで,最速のタイミングで受け身が取れるシステム。BBシリーズやP4Uシリーズのほか,多くのタイトルで採用されているが,GGXrdでは復帰のタイミングを狙って押す必要がある。
パチ氏:
実を言うと,個人的にはGGXrdも“その方向”に行くべきじゃないかと思っています。それは初心者向けというより,少なくともアークゲーという括りの中では,操作の規格を統一すべきだろう,という理由からなんですけど,そのほうがほかのタイトルから移行しやすいじゃないですか。なので,とくに受け身については開発当初から“押しっぱ派”だったんです。
4Gamer:
そうだったんですね。
パチ氏:
ただ(ゼネラルディレクターの)石渡には,“これまでのシリーズ作品から操作感を変えたくない”という強い想いがあって。結果,落としどころとして先行入力の受付時間を延長するという道を選びました。でも,石渡がこだわる理由もよく分かるんです。例えば GGXrdで押しっぱ受け身を実装したらどうなるかというと,まず初心者同士の対戦では,ほとんどコンボを最後までつなげられなくなる。
4Gamer:
ああ,必ず最速受け身ができてしまうわけですものね。
パチ氏:
ええ。「相手が受け身をミスったおかげで勝てた! ラッキー!」ってことが起こらなくなり,それによって決着がつきづらくなる。簡単にしたことによって,不便な部分が出てくるので,仕様としては一長一短なんですよ。それは必殺技のコマンドやコンボなんかにも言えて,「簡単にしてほしい」という声に応えるのは,実はそう難しいことではなかったりする。でもそれで本当に面白くなるのかといえば,自分はやや懐疑的です。難しさを乗り越えてこそ得られる感動だって,やっぱりあるわけですから。
4Gamer:
石渡さんのこだわりは,ご自身のそうした感動に根ざしたものであると。
パチ氏:
格ゲーをやっている人なら,皆感じているはずなんだけどね。シンプル操作がトレンドではあるけれど,完璧なタイミングと難しい操作を要求されることも,格ゲーという遊びの根幹の一つではある。そこを完全に否定してしまうのは,ちょっと違うかなと。
4Gamer:
コンボが長くて難しいことが,格闘ゲーム初心者のハードルとして挙げられることが多いですけど,あれも元々は初中級者への救済措置なわけで。もちろん,無駄に長かったり,無駄に難しいのは困りものですけど。
パチ氏:
コンボならトレーニングモードにこもって練習していれば一人でも上達できるけど,差し合いに強くなろうと思ったら,それこそ山のような対戦と,システムに対する理解が求められるわけで。その側面から見れば,いわゆるコンボゲーのほうがはるかに優しいゲーム……とも言えるんだよね。極論ですけど,ストリートファイターで「ウメハラに中足(払い)を10回当てるのと,1回当ててフルコンボを入れるのとで,どっちがまだ目があるか」って思いません? まあ,それぞれ別種の難しさなんで,一概には比べられませんけどね。
 |
未来の格闘ゲームはどうなる?
4Gamer:
フランスパンさんは,格闘ゲーム初心者向けの電撃FCと,コア向けのUNIの2本を手がけていますが,ともにゲージ周りが特徴的だと感じています。上達すればするほど,ゲージ管理が重要になってくるという。これは格闘ゲームの駆け引き――メカニクスとしては,結構新しいのではないかと思うのですが,いかがですか。
鴨音氏:
そうかもしれません。思想としては,どちらも「うまい人がうまいプレイをしたときに,それがちゃんと評価されるゲームにしたい,というのが根幹にあるんです。さっきの話にもありましたが,例えば難しいコンボを大会で決めたりすると,やっぱり盛り上がるじゃないですか。でも,例えば見切りにくい中段攻撃をガードしたとか,抜けにくい投げを抜けたとかだと,その凄さはなかなか伝わらない。
4Gamer:
そのタイトルのコアなプレイヤーでもない限り,難しいでしょうね。
鴨音氏:
それがゲージという形で視覚化できたら,もっとプレイヤーにも注目が集まるんじゃないかって考えたんです。あるいは初心者が失敗してしまったときに,何が悪かったのか,反省すべき点が分かりやすいという効果もありますし。
4Gamer:
格闘ゲームにはコンボがうまいという以外にも,いろいろな強さがありますからね。防御が異様にうまいとか,ジャンケンがやたら強いとか。そういうプレイヤーにも,もっとスポットを当てたいと。
鴨音氏:
ええ,UNIのGRDゲージは,まさにそんなことを考えて作ったシステムだったりします。ただまあ,これも突き詰めればネガティヴペナルティの裏返しのようなものなので,それほど新しいアイデアというわけでもないんですよね。格ゲーの鉱脈は,もうすでにかなりのところまで掘り尽くされているので,新しいゲームシステムなんてそうそう出てくるものでもないのかも。
 |
4Gamer:
格ゲーの歴史を振り返ってみると,色々なアイデアが生まれては消え,洗練されたものだけが残っているように思えます。しかし,そんな中にはまだ発展の余地があるものも残されているんじゃないかって気もしているんです。
パチ氏:
個人的には,「バーチャファイター3」に採用されたアンジュレーション(地形による高低差)なんかは,2D格闘ゲームに応用できるんじゃないかって思いますね。単なる高低差だけでなく,“フィールドありきの2D格闘ゲーム”という意味で。
マスクマン1号氏:
「インジャスティス:神々の激突」なんかは,ちょっとそれっぽかったよね。ただ,2D格闘ゲームのステージ要素って,概ね不評だった気がするけど。「リアルバウト餓狼伝説」のリングアウト然り。
パチ氏:
それはシステム的に後付けだったからじゃない? 最初からステージやアンジュレーション込みでデザインしたものなら,新しい対戦ゲームとして成り立つかもしれない。個人的には,「サイキックフォース2012」のサドンデスシステムが好きだったもので。
4Gamer:
それはどういうものだったんですか?
パチ氏:
タイムアップになるとステージが狭くなって,お互いの体力がドット(極小)の状態から再スタートになるんだけど,一度でもサドンデスが発生すると,その後は対戦が終わるまでステージが若干狭くなるんだよね。当時使っていたのが接近戦キャラだったから,相手が遠距離キャラだったときは,まず最初のラウンドでサドンデスに持ち込むのが戦略になってたんだ。
 |
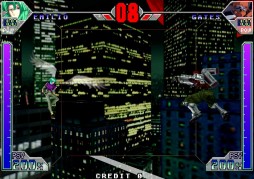 |
4Gamer:
接近戦が得意なキャラは,なんとかしてサドンデスに持ち込もうとし,一方で遠距離戦が得意な側は,なんとしてもK.O.勝ちを狙う必要があるわけですね。
パチ氏:
そうそう。サイキックフォースは守りが強すぎるゲームで,実力が同等だと,どちらかが本気に守りに入るとサドンデスになりがちだったんだ。そこは嫌だったんだけど,なんとか時間内にケリをつけようとする,そこの駆け引き自体はすごく面白かった。“自分に有利なステージを作る”という要素は,立ち回りの延長線上にあってしかるべきなので,そういうギミック込みの格闘ゲームは作ってみたいかな。
4Gamer:
ハードウェアの進化による発展はどうでしょうか。個人的には,フレームレートを120fpsに引き上げて格闘ゲームを作るとどうなるのかなんて,ちょっと気になるところです。バーチャファイターが「2」になって60fps化したときは,かなりの衝撃がありましたし。
パチ氏:
GGXrdみたいに3Dグラフィックスのゲームなら,そういう方向の進化もありえるでしょうね。でも2Dグラフィックスだと,そろそろ限界が近いと思います。解像度にしたって,今はどこも720pで作ってますが,次にネイティブ1080pで作れって言われても,恐らく無理でしょう。
マスクマン1号氏:
120fps化したとしても,30fpsが60fpsになったときほどの,コストに見合った気持ちよさが出せるかどうかは分からないですね。フルアニメーションがしっくりこなくて,リミテッドアニメーションを選択したGGXrdの例もありますし。
鴨音氏:
2D格闘ゲームで,これ以上グラフィックスを強化しようとするとかなり苦しいんです。単純に描くのが大変ですし,スペック的にもメモリに乗り切らなくなる可能性も出てくるという。
マスクマン1号氏:
単純にバトルデザインだけ見るなら,「発生4フレームだと強すぎるんだけど,5フレームだとちょっと」というときに,60fps換算で4.5フレームにできるのが,便利といえば便利かもしれない(笑)。
4Gamer:
今よりもさらに精密な操作が要求されるゲームになってしまうかも?
鴨音氏:
だからこそ面白い,という可能性もありますけど。
パチ氏:
いっそ,Oculus RiftやPlayStation VRのVR-HMD対応にして,「機動戦士ガンダム 戦場の絆」みたいなインターフェイスで,サイキックフォースや「旋光の輪舞」みたいな超能力バトルものにしたら面白いんじゃない。それでレバーをガチャガチャやったら,超リアルな波動拳が出せるっていう。
4Gamer:
「バーチャロン」みたいな? というか,それもはもう格闘ゲームと呼んでいいのかどうかすら分からないですけど(笑)。
鴨音氏:
革新的なシステムなり,バトルデザインなりを取り入れると,皆がイメージする”格闘ゲーム”からはどんどん離れていく。そこが格闘ゲーム作りの難しいところなんですよ。
4Gamer:
夢の膨らむお話ですが,そろそろお時間のようです。最後に,各々の作品のファンに向けて,メッセージをお願いできますか。
遠藤氏:
BBシリーズの最新作「BLAZBLUE CENTRALFICTION」がもうすぐ稼働ですので,ぜひお楽しみに。また,Steamでは「バトルファンタジア -Revised Edition-」「アルカナハート3 LOVE MAX!!!!!」が好評配信中です。そして2016年1月下旬には「スカルガールズ 2ndアンコール」も発売になります。カートゥーン調の可愛いキャラクター達が大暴れするユニークな対戦格闘ですので,ぜひご期待ください!
鴨音氏:
「UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[st]」と「電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION」が稼働となりましたので,ぜひプレイしてもらえると嬉しいです。あと,「月姫リメイク」の話が進んでいることも発表になったようなので,メルブラにもぜひ期待して頂ければ(笑)。
マスクマン1号&2号氏:
P4Uから格闘ゲームを初めてくださった方は,ぜひ一度,大会などのイベントに参加してみてもらえたら嬉しいです。腕前は関係なく,それだけでコミュニティの発展につながるので,アグレッシブに行ってみてください!
パチ氏:
結構いろいろぶっちゃけましたが,格ゲーを熱く盛り上げたいのはメーカーもプレイヤー同じだと思っていますので,一緒に楽しんでいきたいです。あと,好評稼働中の「GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-」も,ぜひよろしくお願いします。
4Gamer:
本日はありがとうございました!
アークシステムワークスとアトラス,そしてフランスパン流の格闘ゲームの作り方について,現場からの生の声を聞くことのできたこの座談会。なかでも,「バトルデザインは世界観や見た目からの要求で決まる」といった辺りは,格闘ゲームにおけるビジュアル要素(=キャラクター性)の重要性を裏付けるような,個人的にも興味深いトピックだった。
「日本のアニメのバトルシーン自体,空中を走るキャラクターも多いですから」とは鴨音氏のことばだが,そうして考えてみれば,モータルコンバットシリーズにワープ技が多い理由も,“世界観の好み”にありそうな気がしてくる。この辺りは,機会があればさらに掘り下げてみたいものである。
ともあれ,冒頭にも述べたとおり,今年から来年にかけて,数々の新作格闘ゲームが稼働/発売を控えている状況がある。格闘ゲーマー諸氏はぜひ新作をプレイし,彼らバトルプランナーの仕事振りをその目と指で確かめてほしい。
なお,今回の座談会のすべての参加者から,「意見を送っていただくときは,なるべく綺麗な言葉で書いてもらえるとありがたいです」との言付けをもらったので,格闘ゲーマー諸氏は,ぜひ心の片隅に留めておこう。
 |
「GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-」公式サイト
「BLAZBLUE CENTRALFICTION」公式サイト
「電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION」公式サイト
「アンダーナイト インヴァース エクセレイト」公式サイト
「ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド」公式サイト
- 関連タイトル:
 GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-
GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-
- 関連タイトル:
 GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-
GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-
- 関連タイトル:
 GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-
GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-
- 関連タイトル:
 GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
- 関連タイトル:
 GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
- 関連タイトル:
 GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
- 関連タイトル:
 BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
- 関連タイトル:
 BLAZBLUE CENTRALFICTION
BLAZBLUE CENTRALFICTION
- 関連タイトル:
 BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA
BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA
- 関連タイトル:
 BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
- 関連タイトル:
 BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
- 関連タイトル:
 BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
- 関連タイトル:
 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION
- 関連タイトル:
 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION
- 関連タイトル:
 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION
- 関連タイトル:
 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION
- 関連タイトル:
 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX
- 関連タイトル:
 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX
- 関連タイトル:
 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX
- 関連タイトル:
 UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late
UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late
- 関連タイトル:
 アンダーナイト インヴァース エクセレイト エスト
アンダーナイト インヴァース エクセレイト エスト
- 関連タイトル:
 アンダーナイト インヴァース
アンダーナイト インヴァース
- 関連タイトル:
 アンダーナイト インヴァース エクセレイト
アンダーナイト インヴァース エクセレイト
- 関連タイトル:
 ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド
ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド
- 関連タイトル:
 ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド
ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド
- 関連タイトル:
 ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ
ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ
- 関連タイトル:
 ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ
ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ
- 関連タイトル:
 ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ
ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ
- この記事のURL:
キーワード
- ARCADE
- ARCADE:GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-
- アクション
- アークシステムワークス
- ファンタジー
- 格闘
- 対戦プレイ
- 日本
- PS4:GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-
- PS3:GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-
- PS3:GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
- ARCADE:GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
- PS4:GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
- Xbox One:BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
- Xbox One
- ARCADE:BLAZBLUE CENTRALFICTION
- ARCADE:BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA
- PS3:BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
- PS4:BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
- PS Vita:BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
- ARCADE:電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION
- PS4:電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION
- PS4
- PS Vita:電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION
- PS3:電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION
- ARCADE:電撃文庫 FIGHTING CLIMAX
- PS Vita:電撃文庫 FIGHTING CLIMAX
- PS Vita
- PS3:電撃文庫 FIGHTING CLIMAX
- PS3:UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late
- ARCADE:アンダーナイト インヴァース エクセレイト エスト
- ARCADE:アンダーナイト インヴァース
- ARCADE:アンダーナイト インヴァース エクセレイト
- ARCADE:ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド
- PS3:ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド
- Xbox360:ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ
- Xbox360
- ARCADE:ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ
- PS3:ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ
- PS3
- インタビュー
- ライター:ハメコ。
- カメラマン:佐々木秀二
- 企画記事
(c) ARC SYSTEM WORKS
(C) ARC SYSTEM WORKS
(C) ARC SYSTEM WORKS
(C) ARC SYSTEM WORKS
(C) ARC SYSTEM WORKS
(C) ARC SYSTEM WORKS
(C)ARC SYSTEM WORKS
(C) ARC SYSTEM WORKS
(C) ARC SYSTEM WORKS
(C)ARC SYSTEM WORKS
(C)ARC SYSTEM WORKS
(C)ARC SYSTEM WORKS
(c)SEGA (c)2014 KADOKAWA アスキー・メディアワークス
(C)SEGA (C)2015 KADOKAWA アスキー・メディアワークス
(C)SEGA (C)2015 KADOKAWA アスキー・メディアワークス
(C)SEGA (C)2015 KADOKAWA アスキー・メディアワークス
(C)SEGA
(C)2014 KADOKAWA アスキー・メディアワークス
(C)SEGA (C)2014 KADOKAWA アスキー・メディアワークス
(C)SEGA (C)2014 KADOKAWA アスキー・メディアワークス
(C)FRENCH-BREAD / ARC SYSTEM WORKS
(C)FRENCH-BREAD / ARC SYSTEM WORKS
(C)ECOLE / FRENCH-BREAD
(C)ECOLE / FRENCH-BREAD
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.
(C)Index Corporation 1996,2011 Produced by ATLUS
(C)Index Corporation 1996,2011 Produced by ATLUS
(C)Index Corporation 1996,2011 Produced by ATLUS