イベント
[SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / [SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/002.jpg) |
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / [SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/003.jpg) |
Quadro RTX 6000は「Project Spotlight」を30fpsで描画できる
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / [SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/004.jpg) |
SIGGRAPH 2018のNVIDIAブースでも,同じデモが出展されていたわけだが,Quadro RTXが発表されたあとに見ると,見え方が変わってくるように思える。GDC 2018時点のProject Spotlightをデモするには,Volta世代GPUベースの数値演算アクセラレータ「Tesla V100」を4基搭載し,15万ドルもする「DGX Station」が必要だった。それに対して今回は,普通のPCにQuadro RTXのミドルクラスとなる「Quadro RTX 6000」を1枚搭載したシステムで,同じデモを同等以上の性能で動作させていたのだ。
ブースにいた説明担当者によると,今回展示しているバージョンは,GDC 2018で公開されたものと基本的には同じ1920×1080ピクセル,30fpsで動作するものとのこと。1ピクセルあたり5本程度のレイをキャストして,影生成や鏡像生成,Ambient Occlusionなどをレイトレーシングで描画しているそうだ。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / [SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/005.jpg) |
Quadro RTXを使ったレイトレーシングの新しいデモが披露
Quadro RTXの発表に合わせて,初お披露目のデモも披露されていた。
そうした新作デモの1つに,ゲームグラフィックス用途を想定したデモがある。宇宙飛行士がロボットアームとダンスを踊るというシュールなこのデモは,担当者によると,ゲームエンジンで映像を制作する映像作品向けのサンプルにもなっているという。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / [SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/006.jpg) |
この技術デモは,UE4を使用したもので,レイトレーシングで鏡像の生成や影生成,Ambient Occlusionを行う一方で,それ以外の要素はProject Spotlightと同様に,従来型のラスタライズ法を使って描画している。レイトレーシング法とラスタライズ法を組み合わせた,ハイブリッドレンダリング手法による映像というわけだ。
このデモで注目すべきポイントは,Project Spotlight同じく鏡像(リフレクション)の生成だろう。レンダリング結果から映り込みとしての鏡像を疑似生成する定番テクニック「Screen Space Reflection」(スクリーンスペースリフレクション,以下 SSR)では表現不可能な画面外情景の映り込みや,カメラ(視点)に向いているオブジェクトの面に,カメラからは見えない情景が映り込んでいる様子が,このデモにおける一番の見どころである。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / [SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/008.jpg) |
一方で,ラスタライズ法で描画するオブジェクトで目立っていたのがパーティクル群だ。
水蒸気のような「もや」は,法線マッピング的な疑似立体陰影と透過表現を組み合わせた半透明エフェクトを四辺形ポリゴンに描画したものとして,画面内に多数登場する。デモを見ていると,このようなもやは,レイトレーシングで描画する鏡像には,あまり描かれていないことに気付いた。つまり,パーティクル群はレイトレーシングによる描画処理の対象外となっているのだろう。
レイトレーシングでまじめに気体を描画しようとした場合,密度データをもとにした流体物として扱うボリュームレンダリング的なアプローチが必要となるが,このデモでは一般的なゲームグラフィックスと同じく,四辺ポリゴンベースのスプライト的な描画となっているわけだ。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / [SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/009.jpg) |
ユーザーの目が慣れてくれば,こうした要素も描画の粗(あら)として気になるのかもしれないが,少なくとも現時点では,鏡像の正確性に目を奪われるので,あまり気にならないのではなかろうか。
もう1つのデモは,建築デザインや都市開発シミュレーションを想定した技術デモだ。
このような用途において,屋外の情景は日照条件のシミュレーションが,屋内の情景は調度品の配置や材質,窓や照明の位置などが関わる複雑な環境光の正確な表現が重要になる。とくに欧米の建築では,屋内の照明器具が放つ光だけでなく,照明の光が壁などに反射した間接照明を重視する傾向があるし,最近では,天窓から降り注ぐ陽光を効果的に取り入れて,電気による照明を節約するようなデザイントレンドも生まれているそうだ。そこで役立つのが,レイトレーシングを活用した間接光シミュレーションである,というわけだ。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / [SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/010.jpg) |
ブースで見たデモでは,鏡面材質に映り込む鏡像はもちろんのこと,拡散反射による間接光までレイトレーシングで処理していた。仮想空間における太陽を動かすことも可能で,屋外から差し込む陽光が室内をどう照らすかも確認できる。天窓から降り注ぐ光が床の赤いカーペットに反射して,白い壁が淡い赤色で染まったり,間接光が届かない部分はやや暗くなったりといった具合に,間接光の変化を確認できるのだ。
NVIDIAがレイトレーシングの利点としてアピールしている鏡像生成も行われており,鏡面材質でできた犬のオブジェに,カメラの背後(※つまり視界外)にある部屋の情景が映り込んでいる様子も表現できていた。
この技術が一般化すれば,たとえば引っ越し先の住居を選ぶときに,部屋の間取りだけでなく窓の大きさや位置,時間帯ごとの部屋の明るさや照明器具の配置などを決めるのがたやすくなりそうだ。
オフラインレンダリングもQuadro RTXで高速化
Quadro RTXの発表では,レイトレーシング技術をリアルタイムグラフィックスにもたらすことが大きなトピックとなった。しかしNVIDIAは,映画制作のようなオフラインレンダリング用途に対しても,作業の高速化を実現する手段として,Quadro RTXを強くアピールをしている。
オフラインレンダリングにおけるQuadro RTXの活用事例としてブースで披露されていたのが,ポルシェのコンセプトモデルである「Porsche 911 Speedster Concept」のデザインプレビューデモだ。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / [SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/011.jpg) |
車のデザイン工程では,実寸の模型を制作する前に,コンピュータ上でデザイン評価を繰り返すのだが,評価のときには,さまざまなライティング条件で車の見え方を検証する。フロントフェンダーの峰のうねりや,側面ドアを横切る凹凸のラインなどは,ライティング条件を変えると見た目が結構変わってくるため,自動車のデザインではとくに念入りに評価される。
こうした評価では,当然ながらレイトレーシングでレンダリングを行うのが主流なのだが,与えたライティング条件で描画が完了するまで,今まではかなり待たされていた。これがQuadro RTXの登場により,ほぼリアルタイムにライティング条件の変更を適用してデザイン検証が行えるというのが,このデモのメインテーマなのだ。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / [SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/012.jpg) |
このデモでは,レイ数が不十分なのか,あるいはレンダリング時間が足らないためなのか,レイトレーシング結果からノイズを除去する「デノイザ」(関連記事)を使っていたのだが,よく見てみると,鏡像のデノイズ処理が安定しておらず,時間方向にちらつく現象が見られた。
この点について質問してみると,現状のデノイザは複数フレームに渡って処理する(≒時間方向の処理を段階的に進めていく)アーキテクチャのため,悪条件では,このような状況になることもあるのだとか。
もっとも,大抵の場合,レイトレーシング結果に対するデノイズ処理は,デザイナーやアーティストが制作途中の評価に用いる用途を想定している。納品する最終映像は,たっぷりと時間をかけてレンダリングするので,多くの場合は問題にならないというのが,NVIDIAの考えであるようだ。
とはいえ,ゲームグラフィックスでも,こうした時間方向のチラツキは望ましくないだろう。たとえば,ゲーム用途ではデノイズ処理のフィルター径を大きくするとか,サンプル数を増やすといった個別チューニングが必要になってくるかもしれない。
業務用途におけるレイトレーシング技術の活用を想定したデモとしては,ディズニー&マーベルの人気特撮映画「アベンジャーズ」から,スパイダーマンの映像をQuadro RTXで描画するものも披露されていた。
こちらは,単体で動作するデモではなく,Autodeskの3Dグラフィックス制作ソフト「Maya」のプレビュー画面用レンダラーをNVIDIA RTXベースのレンダラーに変更し,プレビュー画像をQuadro RTXで描画するというものだ。
デモのコンセプトは,ポルシェのものと同様,アーティストがライティング設定や材質変更を行うときの評価用として,最終納品映像に近いテストレンダリング結果を短時間で得ることを目的に,Quadro RTXで高速化したレイトレーシング環境を実現するものである。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / [SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/013.jpg) |
このデモもデノイザでノイズを低減することで,短時間で最終映像に近い画像を出力していた。その時間はわずか1〜2秒程度だ。ゲームグラフィックスの感覚だと0.5〜1fpsは遅く思えるが,この品質の映像を生成するのに,従来は数十分はかかっていたというのだから,アーティストからすれば,圧倒的な高速化を実現できたという感覚なのだ。
デモの担当者も,「従来は,時間短縮のためにプレビュー画像を小さく(=低解像度で)出力する工夫を行うことも多かったが,小さい画像では細部のライティング結果やテクスチャの見え方などが確認できない問題があった」と述べていた。しかし,Quadro RTXの環境であれば,高解像度でレンダリングしても数秒しかかからないので,「作業の高速化は計りしれない」そうだ。
レイトレーシングはサウンドにも応用可能
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / [SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/014.jpg) |
デモで使用していたのは,NVIDIAの多人数同時参加型VR会議システム「Holodeck」(関連記事)だが,機械学習ベースのアニメーションシステムで,映像内に出てくるアバターは,手足の付いたロボットのような姿で描かれるようになった。以前のバージョンは,アバターの顔と手,胴体だけを描画していたので,より人間に近いアバターを表示できるようになったわけだ。
筆者が体験したデモは,小さな会議室に設置したスピーカーから出る音を,会議室の中や外で聞いたり,会議室のドアを開閉して聞こえ方を確認したりという内容だった。
会議室の中では,残響の効果でややエコーを感じる聞こえ方となる。一方,部屋の外に出ると,開け放したドアから強い音が聞こえるのに加えて,壁ごしにもこもった音が聞こえるといった具合だ。ドアを閉めれば,全体的にこもった音になるので,壁の向こうで音が鳴っているのが分かる。
デモの途中で,壁の材質が木材から絨毯のような素材に変わると,音の聞こえ方は一変した。絨毯の壁は音を吸収してしまうので,残響は聞こえなくなるのだ。音波の伝搬シミュレーションを,Quadro RTXによるレイトレーシング的な処理で実現できるというのが,このデモの見どころである。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / [SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/015.jpg) |
実装としては,スピーカー(≒音源)の位置から発生する音をレイに置き換えて,放射状に射出する仕組みだ。スピーカーは前面から強い音が鳴るので,レイの放射強度は,スピーカー前面が強い非対称形状となる。
発生したレイは,3Dシーン内のさまざまなオブジェクトに衝突して,反射を繰り返す。木材のような硬い材質に囲まれた部屋では,レイが鏡面で反射するように音が反射しまくるので,これが残響として聞こえる。一方,絨毯では音波が吸収されて減衰し,壁に衝突した音波は波形が歪んでから壁の外に伝搬するので,こもって漏れ聞こえるような音になるわけだ。
担当者によると,音のレイトレーシングは,グラフィックスよりも射出するレイの数が少なくて済むとのこと。反射や吸収,回折といった現象の処理系も,グラフィックスに比べれば演算負荷が軽いので,グラフィックス以上にゲームのようなリアルタイムアプリケーションへの応用活用は進むはずだ。
GeForce版Turingの登場に期待が高まる
GDC 2018のNVIDIAブースもレイトレーシング1色だったが,「DirectXに採用されたことで,今後はレイトレーシングが身近になっていくかも」という期待感と,「リアルタイムでレイトレーシングができるといっても,1台約15万ドルのDGX Stationが必要ではな……」というお預けを食らったような印象がない交ぜとなっていた。それに対して今回のQuadro RTXは,お預け感を一気に払拭して,RT Core搭載GeForce登場への期待が高まったように思う。
そうは言っても,一番安い「Quadro RTX 5000」でさえ2300ドル(税別)もするので,今はまだ,Turing世代GPUはゲーマーから縁遠い存在だ。RT Core搭載GeForceが登場するとして,それがいつ,どんな形で出てくるのかという疑問も,今はまだ答えは出ていない。
8月14日には,次世代GeForceを予告すると思われる意味深なティザームービーも公開されており,ゲーマーとしては,期待が高まりすぎて破裂してしまいそうだ。今後の展開が楽しみでならない。
NVIDIAのSIGGRAPH 2018特設Webページ(英語)
- 関連タイトル:
 NVIDIA RTX,Quadro,Tesla
NVIDIA RTX,Quadro,Tesla
- この記事のURL:
Copyright(C)2010 NVIDIA Corporation


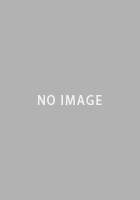






![[SIGGRAPH]「Turing」で始まるリアルタイムレイトレーシングの時代に期待が高まったNVIDIAブース](/games/121/G012181/20180817114/TN/001.jpg)









