イベント
[CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/001.jpg) |
大塚氏は元麻薬取締官という異色の肩書きを持ったアニメーターで,伝説の「白蛇伝」(1958)や「太陽の王子 ホルスの大冒険」('68)に参加,「ムーミン」('69)「ルパン三世」('71)「パンダコパンダ」('72)「未来少年コナン」('78),映画「ルパン三世 カリオストロの城」('79)「じゃりン子チエ」('81)などの作画監督を歴任してきた,いわば伝説級の人物。
上田氏は,「ICO」「ワンダと巨像」「人喰いの大鷲トリコ」といった,日本だけでなく世界が認める異色傑作のディレクター・ゲームデザイナーだ。
細田氏は「未来少年コナン」「みつばちマーヤの冒険」「名犬ジョリー」といったアニメーション作品に参加したのち,草創期の2D/3DCGオペレーションを担当,現在はバンダイナムコゲームス社長室に所属している。
それぞれ作品名だけ見ても豪華絢爛,超大物クリエイターの揃い踏みである。
アニメの力をゲームへと
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/003.jpg) |
そもそもゲームは,30年前は非常に未成熟なもので,貧弱な表現力を「どのように補っていくか」に主眼が置かれていた。だがハードが進化し,フォトリアリズムの達成やモーションキャプチャの導入,物理シミュレーションといったものが実装された今,「ではいったい『リアル』とは何なのか?」という問題が逆に浮上している。演技としてのリアルさと,実像としてのリアルさは異なるものなのだ。
そこで,かつてさまざまな不便があった時代に,工夫を重ねて欧米と渡り合った表現力を,もう一度立ち戻って学んでみよう――それが今回のセッションの趣旨というわけだ。
……とはいえ,ステージに大塚康生氏がいるとなると,自然と話題は大塚氏に集中する。ということで,今回の対談自体がかなり大塚氏の語りに偏っていたことを,前もってご容赦いただきたい。
「動いて初めてアニメーション」
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/002.jpg) |
そこで氏は,厚生省の試験を受けてこれに合格,麻薬取締課で補佐として4〜5年を勤める。麻取というとさまざまな危険な捜査が思い浮かぶが,氏曰く「補佐だったので,調書を作ったりするなどの書類仕事」が主だったそうだ。
昭和57年,東映がアニメ事業を始める。それまで外国製のアニメーションを見てきた大塚氏は,その美しさ,華麗さに魅せられていた。そこで東映に行き,試験を受けることにする(「受けることにする」と簡単に言ったが,公務員から,未だ行き先の定まらない業界への転身であることは,見落としてはいけないだろう)。
そこでの試験は非常に実践的なもので,少年が槌を持っている絵が描かれていて,「この少年が槌を振り上げて,振り下ろす,その過程の絵を6枚描け」というものだった。氏は即座に着手しようとしたが,試験官がそこで「この槌は非常に重く,少年がやっと持てるほどだ」と言い添えた。
大塚氏は,ここでじっくり考える。それほどまでに重いものを持ち上げて,振り下ろすとなると,ただ単に槌を持った手(と槌)が上がって下がるではいけないのではないか,と。かくして,足を一歩踏み出し,左肩が上がり,また持ち上げてもそう高くは持ち上がらない……そんな絵を仕上げた。試験官には,この「肩を引いて腰をためる」という動きが評価され,即採用ではなかったものの,練習に通うように言われたという。大塚氏の,アニメーター人生の始まりである。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/016.jpg) |
もともと氏は蒸気機関車が好きだったという。蒸気機関車は「アナログの塊」で,動作が外からもよく見える。そうして,「なぜ動くのか」「どう動くのか」「前進と後退の切り替えはどう行われているのか」という疑問を抱き続けた氏は,ついには機関士に直接尋ねることまでした。
この動作への探究心は,人間に対しても発揮される。そして氏は,人間にも作動原理があると説き,必ずしも絵が重要なのではないと述べた。
ちなみに大塚氏は,東映で11年間勤務したが,その間に手がけたのは「火を吐く大蛇」「なまず」「雷魚」といったおどろおどろしいものばかりで,「女の子はワンカットも手がけていない」という。氏の目には,機関車や人間だけでなく,大蛇やなまずの作動原理も見えていたのだ――のちにムーミンを手がけたときには「こんな可愛いものが描けたのか!」と驚かれ,ルパンで峰不二子を描いたときにも同じように元同僚から驚かれたという。「描けないんじゃない,受け持ったパートにそういう絵がなかっただけなんだ」とは氏の言葉である。
作動原理を重視する大塚氏は,当然ながら「動く絵」を重視する。「動いて初めてアニメーション」という当たり前の言葉には,しかし重みを感じざるを得ない。
大塚氏は現在「アニメ塾」の塾長を務めているが,「今はみんな絵が綺麗で上手い。10人中9人は上手いと思う」と語る。綺麗な絵を描くための情報が,昔と比べて増えたのだ,と。
半面,絵を動かすことに興味のある人は減っていると氏は感じている。「テレビアニメがまともに動かない。アニメーターが動く絵を描けない。(槌の例で言えば)槌を振り上げたカットと振り下ろしたカット,2カットを並べて『動かしたこと』にしてしまう」と現状を嘆き,「これが今のアニメーションの活力を削いでいるのではないか。表現の綺麗さが増すばかりで,しつこさが減っている」と指摘する(実際,今のアニメは「ルパン三世」時代の2/3程度の絵の枚数で作られているらしい)。
そして,CGが自由に絵を動かせることを踏まえ,「動く絵に興味のある人は,これからどんどんアニメではなくCGに行くかもしれない」と語った。
「アニメーションとは,なりきること」
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/004.jpg) |
上田氏は長じてゲーム業界に入るが,そこで大塚氏の『作画汗まみれ』を読む。そしてゲームの世界でアニメーターが軽視されている状況を見て,これではいけないと思ったという。
そこで上田氏が取り組んでいるのが,大塚氏が最初に受けたという試験と似たような実技テストだ。これは時間を区切って(3時間程度),一定の動作をする3DCGアニメを作るのが課題だと言う。会場では上田氏が3時間で作ったという「バーベルを持ち上げる動作」が公開され,多くの参加者がその完成度の高さに驚嘆していた。
また上田氏は,「アニメーションとは,キャラクターになりきることだ」と語った。バーベルを上げるのであれば,バーベルの重さを感じさせるために,自分が重いバーベルを持ち上げるその人物になりきって動作を想像する,それが重要なのだと。
バーベル上げの3Dアニメーションは,大塚氏をも唸らせる完成度で,「もうちょっとタメがほしい」としながらも「やっぱりCGは凄い」と感心しきりであった。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/005.jpg) |
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/006.jpg) |
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/007.jpg) |
ちなみにこの「課題」の話をめぐっては,大塚氏から思いがけない逸話も飛び出した。
氏は東映時代の試験をもとに,同じような試験を用意していて,あるときその題材として「飛び込み台からプールに飛び込む男」を描くという課題を出した。すると,ある受験者は,「飛び込もうとしたのだけれど,飛び込み台から下を覗き込み,怖くなって飛び込み台を降りて,そっとプールに入る男」を描いたという。
当然ながらこれは「飛び込む男」の規定から完全に反しているため,スタッフらは彼を非採用とすべきだと主張したが,大塚氏は「彼は絶対に面白い,採用すべきだ」と強硬に主張,結果「飛び込まなかった男」を描いた人物は見事採用となった。大塚氏がその人物に「なぜそんなことをしたのか」を聞いてみると,本人が高所恐怖症であるため,「描いていたらこうなった」らしい。
そうして採用された人物が,杉井ギサブロー氏である――「鉄腕アトム」「ルパン三世」などを皮切りに,「まんが日本昔ばなし」,やがて「タッチ」「あらしのよるに」などを手がけていく人物だ。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/010.jpg) |
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/011.jpg) |
演技するキャラクター
このように,ある意味で「キャラクターに演技をさせる」という観点について大塚氏は,「人をインスパイアするためには,元の人が相応のものを持っていなくてはならない」と言う。
もっとも,キャラクターに演技をさせるために必要なのは,精神論だけではない。ルパン三世では,キャラクターをちゃんと動かすため,各キャラクターの「直立した立ち絵」を作らなかったと語った――ルパン三世の設定画は,みな立ちポーズの重心を変えたという。直立不動の立ち姿が実際の画面に出てくることはまずないし,むしろ「ルパンはリラックスしたポーズが多い」といった個性を出すためには,いわゆる立ち絵ではよろしくないというわけだ。
また,アニメとして動かしやすい絵を作るためには,漫画とは違った技法が必要であると大塚氏は言う。ルパン三世のときは,モンキー・パンチ氏と10日くらいホテルに篭って絵を描いたが,モンキー・パンチ氏は「後ろから見たルパンの絵」が描けなかった。大塚氏はキャラクターを360度ぐるりと回転できるように絵を作ること,つまり「立体的であること」が,アニメのなかで安心して動かせる絵のポイントであると述べた。
実際,「じゃりン子チエ」のときも,漫画そのままだと動かせないが,大塚氏が起こしたキャラクターだと芝居がさせやすいという声があったという。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/008.jpg) |
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/009.jpg) |
キャラクターの演技という問題に対し上田氏は,「ディレクターという立場で言うと,飛び込み台から降りてしまうようなのは困る」と苦笑しつつも,キャラクターになりきっていくという過程を踏めば,それは自然に作り手の性格がキャラクターにも表出することになると語った。「元の人」の持っているものが,現れざるを得ないのである。
また技術論としては,アクションの大きさや強さが伝わる,動きが分かりやすいプロポーションを作ること(大きな体に短い手足といった姿ではダイナミックさが伝わりにくい)や,過剰なくらいディテールを詰め込むことで情報量を現実に近づけ本物っぽさを出す(筋肉をわざと振動させたりする)といった技法があるという。後者は,ディテールを増やしても作画の負担が上がらない,CGならではの技術といえる。
他方,上田氏は「感じるリアリティと実際のリアリティには差がある」とし,アニメはデフォルメや記号化によって少ない情報で「感じるリアリティ」を演出できているのに対し,CGはとにかく現実に近い情報量を詰め込む段階でしかないとした。事実,「人喰いの大鷲トリコ」では,この「過剰なくらいに詰め込む」ことを行っていると言う。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/012.jpg) |
そしてここで,上田氏の3作品(「ICO」「ワンダと巨像」「人喰いの大鷲トリコ」)におけるCGアニメーションが上映されたのだが,それを見た大塚氏が「……すごいですねえ。コンピュータでこんなことできるんですねえ」と,しばし無言で感嘆していたのは,非常に印象的な光景だった。
しかしながら,そうやって最先端のCGアニメーションに驚嘆しつつも,「これはルネサンス以降に生まれた,輪郭線を持たない絵の技法。僕は浮世絵から続く,線の中に絵を描くのが好きだ」と語ったところには,凄いと思ったものを素直に凄いと評価しつつ,それと自身の仕事を相対的に配置できる凄みを感じさせられた。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/013.jpg) |
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/014.jpg) |
止め絵と思い入れ
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/015.jpg) |
日本のアニメーションは,止め絵の効果というものを上手く利用するし,観客もそれを理解している。ところがアメリカでは,止め絵になるシーンでも基本的にキャラクターは動いている。それどころか,ある程度以上に止め絵が続くと,観客は「映写機の故障じゃないか」と考えるらしい。
観客がアニメーション作品のことを慮ってくれるというのは日本独自の文化だが,それは同時に,日本では観客が自分の思い入れを作品に重ねて見ているということでもある。この「思い入れ」の例として,大塚氏は「鉄腕アトム」を挙げた。
大塚氏は,「鉄腕アトムの動きは無茶苦茶で,どんな重たいものでもあっさり投げ飛ばす。アニメーションの面白さとしては,重いものを持ち上げるならぐっと踏ん張ったり,頑張ったりする動作があるべきだが,アトムはそのようなことをしない。なぜなら,アトムは100万馬力だからであり,その『思い入れ』が観客の側にもあるからだ」と語る。
そしてこれに対し上田氏も,「100万馬力と言ってしまうのは簡単。ゲームならそういう設定にすればいいだけだ。でも,そこで本当に100万馬力だと感じさせるのは大変だし,そこにアニメーターの仕事がある。空想に説得力を持たせるには,ディテールに手を加えるという手法はあるが,アニメーションの力が大きい」と述べた。
このように,「日本国内ではなんとなく共有されているもの」に寄りかかった表現を繰り返していたら,いざ世界に持ち出したときにまったく通用しなかったというのは,近年散見される事態だ。この状況を「それは日本独自の文化だから仕方ない」という理由で無批判に受容するのは,いわば受け手の「思い入れ」に甘えているに過ぎない。
これはあくまで筆者の見解だが,大塚氏が止め絵を日本の文化としつつも,それは観客によって許されて初めて成立する(観客に助けてもらっている)ことを示唆し,あるいは上田氏が「設定するだけなら簡単」と断じるように,「日本独自」を(追求するのではなく)単なる免罪符にすることは,表現にとって非常に危険であるといえるだろう。
いつかきちんと評価されると信じて
さて,さまざまに奥の深いアニメーターの世界だが,「ではアニメーターを育成するにはどうしたらいいのか」という論点になると,非常にぶっちゃけたトークが(主に大塚氏から)炸裂する。以下,「いやあそれはちょっとヤバいんじゃないですか」と思わなくもないお言葉を簡単にまとめておく。
――優れたアニメーターを育てるにはどうしたらいいのか
「子供の頃からやらなくてはいけない。20歳ごろから勉強してもダメ。『誰でもアニメーターになれます』みたいな宣伝は良くないんじゃないか。そもそも,アニメーターは,育てるより発掘するものだと思ったほうがいい」
――アニメーターを育てるとして,賞賛と辛口の批評と,どちらがいいのか
「けなして育てたほうがいいでしょう。けなされるほうがありがたいし,学ぶことも多い」
――アニメーターに向いた人,向いていない人を選別できるか
「無理です」
「今まで仕事をしてきたアニメーターには,本当にいろいろなタイプの人間がいた。こういうタイプだから上手くいく,というのはない」
――アニメーターやCGアニメーションを仕事にしようとする人を増やす方法
「ない」
……実に歯に衣着せぬトークである。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / [CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/017.jpg) |
司会の細田氏が言うとおり,ゲームにおけるCGアニメーションは,「動いて当たり前」という部分がある。そこにはキャラクターの芝居,リアリティという課題があるにも関わらず,往々にしてゲームそのものの評価はそれらとは無関係なところで決定される。どんなにアニメーションが優れていても,ゲーム性が壊滅的だったならば,その作品が良い印象を持たれる可能性は極めて低いのだ。そしてその現状を反映して,社内に「アニメーター」という職業が存在しないゲーム開発会社も多いという。
だが,上田氏が指摘するように,日本のアニメーション技術をゲームが上手く取り込めば,それは海外のスタジオに対するアドバンテージとなるだろう。それをどのように実現し,評価していくのか。
日本のアニメーションの力を体現する一人である大塚氏に,その大塚氏をしばし無言にさせるCGを構築する上田氏。その凄みが実感できるだけに,道のりの厳しさと,そこに眠る大きな可能性を予感させる対談であったと言えるだろう。
キーワード
(C)Sony Computer Entertainment Inc.
(C)2016 Sony Interactive Entertainment Inc.



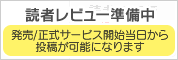







![[CEDEC 2010]アニメとゲームを結ぶ“動かす技術”について,超大物クリエイターが熱く語った。「大塚康生×上田文人対談 〜もっと上手くなりたい!動かす力〜」レポート](/games/093/G009303/20100902018/TN/018.jpg)












