イベント
[GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート
ジャンルとしては「ウォーキングシミュレーター」と定義されるが,ゲーム内にはさまざまな要素が複合して存在している。「とにかく不思議な体験ができる,探索アドベンチャー型のゲーム」とでも紹介するのが無難だろうか。
さて,近年において傑出した「不思議なゲーム」であるEdith Finchだが,それを作ったチームもまた,近年において傑出した「不思議なチーム」であった。Giant Sparrowのcreative directorであるIan Dallas氏がその詳細を語った講演の模様をざっくりと紹介しよう。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/001.jpg) |
登壇したDallas氏は,最初にEdith Finchの大きな構造を解説した。大まかに言えばこの作品は,
・呪われた家族に関する13の物語
・それぞれにユニークで意味深長なゲームプレイを有する
・荘厳な感覚を引き起こすことに集中した作品
ということになる。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/002.jpg) |
Edith Finchは一種のアドベンチャーゲームであり,プレイヤーは「何かを発見した」感覚を得るが,それだけにその「何か」は「発見される」状態になくてはならない。Dallas氏によれば,本作の目的は「プレイヤーの感情をゆさぶる」ことであり,ゲーム的な謎解きや探索は本題ではないのだ。
そのうえでDallas氏は,この講演で3つのトピックを扱うとした。
・経験をデザインするために何をすべきか
・「感覚」を見出し,コミュニケートするということ
・プロトタイプを作るということ
である。
ここまで,GDCの講演としては割と普通の導入なのだが,途中からゲームと同様の不思議な内容が展開されることになる……。
プレイヤーにストーリーを語るのは無理?
さて,Dallas氏は「経験をデザインする」というトピックに踏み込む前に,「Edith Finchというゲームを作ろう」と思い立つに至った根源に触れた。
そもそもゲームにおいて,プレイヤーがどんな体験をするかなど,予測はできない。ましてやEdith Finchのように,あまり類例のない作品――つまりは「いままでにない経験ができるゲーム」――の場合,制作側だって明確に「こんな体験ができます」と断言してゲームを作り始められるわけではない。
つまり「経験をデザインする」と言えば格好はいいが,これは「作る側ですら知らないことを,形にしようとする」という試みなのだとDallas氏は指摘する。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/003.jpg) |
「ゲームにおける体験」が予測し難いのには,理由がある。
例えばこれが映画や演劇であれば,受け取った側がどこに注目するかを,作り手側がコントロールできる。しかしゲームでは,それなりに誘導可能ではあっても(あるいは強制してしまうことも不可能ではなくても),プレイヤーがどこに注目するかをコントロールするのは難しい。
しかもゲームの場合,プレイヤーは「鉄砲を与えられたばかりの幼児」に等しい。
なるほど,筆者もゲーム内のキャラクターが「Aボタンでキックする」ことを知り,そして画面に壺が置いてあれば,とりあえずは蹴ってみようとするだろう。
そうやって壊した壺が実は「ストーリーの帰趨に関わる超重要アイテムであり,それを壊してしまうと話が進まなくなる」などと言われたら,「これはクソゲーだ」と断じるに違いない。
こんな「明らかにヤバい」連中(現実世界において,見ず知らずの場所で見つけた壺をいきなり蹴って壊そうとする人はそうそういない)を相手に,物語を語るわけである。なるほど,Dallas氏が言うとおり「頑張れ」としか言いようがない試みだ。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/004.jpg) |
この難題に対してDallas氏が立てた対策は,以下のようになる。
・そもそも鉄砲を与えるな
・そもそも物語を語ろうとするな
・代わりに,彼らが探索したくなるような興味深い世界を作り,探索するための道具を与えよ
この方針に基いて,Dallas氏たちのチームはEdith Finchのプロトタイプを作っていった。つまり「ゲームを実際に操作するなかで,感情的な経験をするようなもの」を作り出そうとしていったのである。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/009.jpg) |
そして,さらに2つの指針が立てられた。
・ストーリーではなく,コンテキスト(文脈)を活用する
直接的に何かを語るのではなく,「そうではないかと感じられるもの」を画面に並べる。このことをDallas氏は「サイレント映画を作るようなもの」と語った。
・ストーリーではなく,「感覚」からスタートする
「このゲームはこんな物語体験をユーザーに伝えるものなのだ!」ではなく,「こんな感じのゲーム,かな?」というあたりからゲーム制作をスタートする。
実際,Edith Finchは開発当初,ティーンエイジャーによるスキューバダイビングをシミュレートするゲームだったそうだ。永遠にも続くような暗闇の中を潜っていくと,その先に不思議なものが見えてくるというゲームで,確かに最終バージョンのEdith Finchとはだいぶ違うが,「感覚」という面では通じるものがあるような気がする。
そして目指す「感覚」がなんとなく定まったところで,その「感覚」を生み出すようなプロトタイプの制作に入る。非常に早い段階からプロトタイピングに入ったのは,「『感覚』を体験できるものを作るには,膨大な数の工程が必要だと分かっていたから」だという。なんというか,「この山はすごく高いことだけは分かっていましたので,最初から酸素ボンベを用意しました」的な話である。
なお,このように「感覚」に注力したEdith Finchの開発過程において,ストーリーは,あまり顧みられなかったそうだ。それどころか(あるいはその結果でもあるが),ゲームが完成する直前になって,「これってこういう物語じゃないのか!」となり,ほぼ作り直すことになったという。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/005.jpg) |
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/006.jpg) |
「感覚」を精密化し,共有する
さて,このようにして「感覚」を重視してゲームを作る場合,1人で作るのであれば「ブワッとしてモワッ」的なメモで十分機能するかもしれないが,ある程度の人数で作るとなると「ブワッとしてモワッ」ではマズいことになる。
また,そもそも「ブワッとしてモワッ」という「感覚」が,目指すべき「感覚」であるという保証はどこにもない。これが間違いなく「そちらに進んで良い」という確証を得る方法も必要だ。
ということで,Dallas氏はまず「感覚」を発見する方法を,ステップに分けて解説した。
(1)「感覚」を定義する
1〜3単語程度で,「感覚」を言葉にする。Edith Finchの場合,「荘厳さ+親密さ+湿っぽさ」となった。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/007.jpg) |
(2)「感覚」で周囲を包み込む
参考になりそうな本を読み,映画や演劇を見る。音楽を聞く(映画のサントラは特に有効だという。Dallas氏いわく「もし既にその『感覚』を作り上げることに成功している作品があるならば,そこで使われている音楽を踏み台にするのはとても有効だ」そうだ)。会社の壁紙を変える。PCの壁紙を「感覚」に通じるものにする。
このようにして,物理的にも精神的にも,目指すべき「感覚」で周囲を埋め尽くしていく。
ちなみにEdith Finchの開発で最初に作られた「雰囲気のボード」が,下のスライドだ。これを見ると,Dallas氏が語る「『感覚』で包み込む」ということが何を目指していて,どんな効果があるのか,なんとなく感じられる……気がしないだろうか。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/008.jpg) |
(3)イメージショットを作る
至ってラフなもので構わないので,「こんなイメージになる」という動画を作ってしまう。Dallas氏は実に気軽に「動画を作る」と言ったが,本当にそう言ったので仕方ない。以下,実際に作られた動画を見てみよう(いくつかのイメージは(2)で提示された「雰囲気のボード」にあることが確認できる)。
![画像ギャラリー No.033のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/033.jpg) 明かりの中に浮かび上がる,謎の像 |
![画像ギャラリー No.034のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/034.jpg) どこかへと下っていく階段 |
![画像ギャラリー No.035のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/035.jpg) 水と光のイメージ |
![画像ギャラリー No.036のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/036.jpg) 不可視の犬 |
![画像ギャラリー No.037のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/037.jpg) 不思議な展開をするチェスト |
![画像ギャラリー No.038のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/038.jpg) 本,本,本 |
こうして精度が高められ,「感覚」の具体化が進められたが,これはあくまで「ゲームを作る」という航海における,「方向を指し示すもの」でしかない,とDallas氏は語る。
開発者はこの段階において「方向を指し示す」だけではなく,「道中の地図を作り上げる」ことにまで注力しがちだが,氏によれば「地図を作るのは不必要。その作業は極めて困難だし,退屈でもある」と否定する。
むしろここで示された「方向」を元に,次のステップに進むほうが重要だというのだ。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/010.jpg) |
(4)定められた方向性の助けを借りて,現実的なゴールを設定する
Edith Finchの場合,このステップにおいては以下のような具体的な「落としどころ」が定められたという。
・大自然の中にある風景
・入れ子になった物語と,信用できない語り部
・「荘厳」ではなく「圧倒的」であること
3つめは,異様ですらある。「荘厳」は,Edith Finchというゲームの根幹となる「感覚」だったはずだが,それを否定しようというのである。
しかしながらこのステップにおいて,Edith Finchは荘厳というよりも圧倒的であったほうが「感覚」に近く,またそのほうがゲームが作りやすいという結論に至ったという。
つまり,Dallas氏は目指すべき「感覚」の正体を,ここではっきりと掴んだというわけだ。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/011.jpg) |
かくして「感覚」の精密化は終わった。次はこの「感覚」を,チームで共有しなくてはならない。
ここにおいてDallas氏は,またしてもユニークな方針(と実装)を示した。
・ドキュメントは自分のためのもの
「ドキュメントなんて作っても誰も読まねえじゃん」とは,Dallas氏の率直なお言葉である。実に耳の痛い指摘だが,どうやらこれは洋の東西を問わないようだ。
とは言っても,プロジェクトに後から入ってきた人からすると,「これを読んでおけばチームにおける『共通理解』に追いつける」というドキュメントは効果的なので,作らないという選択もまた難しいという。
・部署ごとに言葉が違うほうが重大な問題
アート畑の人はアートの言葉で語り,プログラマはプログラミングで使う概念を用いて語り,音楽畑の人は音楽の言葉で語るという傾向が見られるため,慣れるまでは意思疎通に齟齬が発生することがある。
またEdith Finch制作チームについて言うと,アートやプログラミングといった部門ごとに,進捗管理ツールが異なっていたという。Dallas氏は「ぶっちゃけ正気の沙汰ではない」としながらも,「とはいえすごく小さいチームだったから,皆がそれぞれ慣れているツールでそれぞれ管理してもらった」そうだ。ワーオ。
ほかにもいろいろとあるが,さすがに「仕込み」に時間をかけているだけあって,共有における問題は概ねこの程度だったという。
ただ,それでも問題は残った。発生し続ける各種変更点を,どのようにして共有するかだ。これについては,
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/012.jpg) |
・毎週末に「展示と説明」をする
・チーム全員で現時点のバージョンを遊んでみる
・チーム全員でテストプレイの様子を見る
・展示会に出してみる
・定期的に新しいタスクリストを作る(新しくすると皆が確認するし,喜々としてリストを埋めようとする)
このような対策で乗り切ったそうだ。
また,プロトタイプ制作もまた「感覚」を探索するツールとなるという。Dallas氏によれば,プロトタイプの大きな目的として,「このゲームがどんなゲームになりたがっているのかを探ること」があるというのだ。
何とも面白い表現だが,Edith Finchのような前例が極めて少ないゲームの場合,「今から作る作品のために,参照すべき作品」がほとんど存在しないという事態にぶちあたる。つまり,極論を言えば,「とりあえず作ってみたプロトタイプが,参照すべき唯一の前例」になっている可能性があるのだ。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/013.jpg) |
Edith Finchの場合,プロトタイプを大量に作り直していく中で,表現すべき「感情」がどのようなものであるのかが,以下のように精密化されていった。
・我々の物語は妄想の中で迷子になっていく人々の物語であり,それはプレイヤーに対しても発生する。
・死はネガティブなイメージで受け止められがちだが,それだけに「己の呪われた運命に向かってまっしぐらに進んでいく」ことは,我々のゲームにおける非常に特徴的な瞬間となる。
実にコストのかかる方法ではあるが,Edith Finchに充満する「感情」は,このようにして厳密化され,チームで共有されていったのである。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/014.jpg) |
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/015.jpg) |
プロトタイプ制作,8つの掟
プロトタイプ作成におけるノウハウを,Dallas氏は8つ提示した。順番に見ていこう。
(1)カードに書く
自分の脳内メモリーには限界があるので,思いついたことはどんどんカードに吐き出す。あとで視覚の助けを借りて整理することもできる。
(2)とにかく書く
「このアイデアはつまらないな」と思っても,とにかく書く。どんな状況で思いついたことであっても,まずは書き留めておく。
(3)自分でやる
世の中には便利なツールがたくさんある。Maya,Unity,Adobe Photoshop以外にも山ほどあるので,これらを使い,粗雑でいいから,自分の手で「こういう感じ」を表現する。
(4)一番簡単なツールから始める
資料を探すならFlickerやYouTubeなどが便利。それ以外にもアセットストアで売っているプロトタイプのような,難しいことを勉強しなくても「こんな感じ」を作るくらいなら十分使える素材は多い。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/016.jpg) |
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/017.jpg) |
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/018.jpg) |
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/019.jpg) |
(5)「スプリング」は神
Edith Finchでは,あらゆるところでスプリング(プログラミングで使う関数)が使われている。プレイヤーのカメラ,テキストアニメーション,カメラのフェード,トグルスイッチなどなど,「何かを動かして状況が変化していく」ときは,「スプリング」を使うと途端に動きがスムーズになって,より「それっぽく」なる。手短にプロトタイプを作るにあたっては非常に有用だ。
(6)音楽も神
「感情」を伝えるにあたって,音楽はとても強力だ。その割に後になってBGMを差し替えても,プレイヤーはそうそう気づかない。仮でいいから,適切なBGMを当てておくと効果的。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/020.jpg) |
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/021.jpg) |
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/022.jpg) |
(7)プレイテストで「詰まり」を解消する
何より,プレイテストで「こうしたほうがいいよ」とアドバイスしてくるヤツのことは,原則無視したほうがいい。テスターが何度も同じことを繰り返しているようなら,ゲームに何らかの「詰まりどころ」が存在する可能性が高いが,同時にテスターがどうしようもなくバカである可能性も考慮すべき――それは彼らの人生であり,我々が改善できるものではない。
結局,テストプレイの質はテスターの能力にかかっており,GDCのようなプロが集まるカンファレンスでのテストプレイは極めて有効である。
そのうえで「詰まりどころ」に対しては……
・アクション要素があるなら,複数回ミスしたところで難度を自動的に下げる
・2通り以上のやり方を用意する(はしごの上に立ったとき,「前進したら降りられる」と思ってレバーを前に倒す人もいれば,「はしごを降りたい」と思ってレバーを下に倒す人もいる。この場合の正解は「はしごの上ではレバーを上にしても下にしても「降りる」ようにする)
・時間経過にあわせて各種マーカーを表示するなどして,ガイドをつける
といった対策があり得る。
(8)作り終えるまで,何もかもを作り変え続けろ
つまり,完成は奇跡だ。
この段階に至れば,自分が何を作っているのか理解できる。
この段階に至れば,そのための手段も手にしてる。
この段階に至れば,(たぶん)そうそう起こらない事態が何であるかも把握している。
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/023.jpg) |
![画像ギャラリー No.024のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/024.jpg) |
完成に至る3つの奇跡と,その布石
……ここまでEdith Finchを作ってきた過程を見てきたが,何というか,「よく完成しましたね」という感想を抱いた人は少なくないだろう。
実際,Edith Finchがリリースされるにあたっては,3つの奇跡があったとDallas氏は語る。
第1の奇跡:ボイスオーバーは半分ほど作り直した
ボイスオーバー(ナレーションのテキスト)は,リリースの一週間前にその半分が書き直されている。
第2の奇跡:ベッドルームは一度全部作り直した
最後のベッドルームを作った段階で,これまでのベッドルームがどのようなものであるべきかがようやく分かった。
第3の奇跡:エンディングを作れた
エンディングがどうあるべきか,チームは12か月にわたって考えたが,答えはでなかった。そこにテストプレイヤーとして参加した2人のデザイナーのうち1人が「エンディングはこうあるべきだよね」と提案してくれた。
そしてなんたることか……それは正しかった!
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/025.jpg) |
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/026.jpg) |
![画像ギャラリー No.027のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/027.jpg) |
![画像ギャラリー No.028のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/028.jpg) |
プロトタイプの(8)で触れられたように,ここで示された方法で進めれば,「完成は奇跡」ということになる。
けれど実のところ,この長い長い航海は,最初にたっぷり時間と技術が投下されることによって,かなり精密に「進むべき方向」が定まっている。そしてまた,プロトタイプを詰めていくなかで,「このゲームはこうあるべき」という姿も,どんどん確かなものになっていく。
その積み重ねがあればこそ,曇りのない目を持った人物が「このゲームはこういうゲームだ!」と見抜く瞬間が訪れる。それは魔法の瞬間かもしれないが,そこまで積み重ねてきたものは,裏切らないのだ。
![画像ギャラリー No.029のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/029.jpg) |
![画像ギャラリー No.030のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/030.jpg) |
![画像ギャラリー No.031のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/031.jpg) |
ちなみに現在,Edith Finchを作ったGiant Sparrowは,新作に向けてスタッフを募集しているという(アニメーションプログラマとリードアニメーター)。彼らの次の作品は,「動物の運動が持つ魅惑的な美しさ」についてのゲームだそうだ。我こそはと思う方は,応募してみてはいかがだろうか。
![画像ギャラリー No.032のサムネイル画像 / [GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/032.jpg) |
「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」公式サイト
GDC 2018記事一覧
- 関連タイトル:
 What Remains of Edith Finch
What Remains of Edith Finch
- 関連タイトル:
 フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと
フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと
- この記事のURL:
キーワード
- PC:What Remains of Edith Finch
- PC
- アドベンチャー
- Giant Sparrow
- ホラー/オカルト
- PS4:フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと
- PS4
- イベント
- ライター:徳岡正肇
- GDC 2018
- Game Developers Conference
(C)2017 Annapurna Interactive


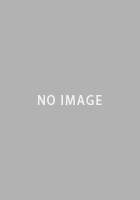
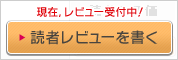






![[GDC 2018]「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」の完成は奇跡だった? 常識外れとも思える開発手法が紹介された講演をレポート](/games/374/G037446/20180323051/TN/039.jpg)








