イベント
[GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/001.jpg) |
まず,稲葉氏は「アクションゲームとはなにか?」という部分から話を切り出した。いわく,「アウトプットに反応する行為の集合」だそうで,ゲームが出力してきた状況(敵が出てきた,攻撃してきた)に対して,一定時間内に適切な対応を要求されるもののことを指すと,アクションゲームの本質について定義した。
なお,ゲームの本質自体は「アクションゲーム」という言葉から感じられるアクティブなイメージのものではなく,プレイヤーはもっぱら受身の立場になることに注意を促していた。
さて,そのような状況の変化に対して逐次反応を返せることがすなわちアクションゲームスキルであるという。プレイヤー側は,慣れてくれば状況を判断して最適の反応ができるようになり,作り手側は反応の受付時間を短くするなどでアクションゲームの難度をコントロールできる。
状況を提示して,それに反応できるかどうかを競うのがアクションゲームの本質だというのはなんとなく納得できる説明ではないだろうか。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/002.jpg) |
アクションゲームのゲームプレイシステムとは
次にアクションゲームを構成する要素についての話が始まった。これは大きく3つに分類できるという。
まず挙げられたのは,「ゲームの売り」になる要素で,これはそのゲームを特徴付けるユニークな要素のことだ。例えば,ベヨネッタでいう「ウィッチタイム」などが相当する。ただ,これは1つだけではダメで,だいたい3つは必要になるという。
なお,1つのウリ要素だけでゲームを作ろうとする人も多いのだが,それをやると絶対に失敗すると氏は断言していた。
次の要素は「拡張性」だ。これはパワーアップであったり,キャラのアンロックであったりといったゲームの横の広がりを増やす要素をことを指す。
最後の一つは「深み」で,コンボシステムなど,プレイヤーが熟練することで価値を発揮するやり込み要素のことを指す。縦方向の広がりを示すものと言ってもいいだろう。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/003.jpg) |
これらを組み合わせて,例えば,
売り要素A/B/C,拡張性D/E,深みF/G
のような7つの軸で構成されたゲームといった感じで設計をしていくそうだ。プロが作るアクションゲームならば,これくらいの数のゲーム要素は必要になってくるという。
さて,これら3つの要素をユーザー体験の面から比較してみよう。売り要素は普通に遊んでいてもすべて見られるだろう。拡張性もある程度やり込めば分かるだろうが,深みについては,場合によってはかなりやり込まないと見られないものもあるかもしれない。
プラチナゲームズの作品の場合,下に挙げたものが見られる人は上級者といってよいそうだ。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/004.jpg) |
しかし,さらにその上もある。
ゲームというものはいろんな人に遊んでもらえるように設計する必要があって,ちょっと遊んでみただけでも十分に楽しめるようにすることが重要だとしつつも,横の広がり,縦の広がりを加えて,ものすごくクレイジーなプレイをする人の要望に応えるように作ることもまた重要だと稲葉氏は語っていた。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/005.jpg) |
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/006.jpg) |
スクリーンには「私にも無理」と稲葉氏が語るようなスーパープレイ映像が展開されていたのだが,開発者自身ができなくても,それができるだけのヘッドスペースが確保されているからこそ,限界に挑戦するゲーマーが出てくるのだろう。
アクションゲームの売り要素はどのようにして作っていくのか
今回紹介された3つの構成要素のうち,最も重要とされるのはゲームの売り要素だ。ゲームの核となる部分をどのように作っていけばいいのかが語られた。
重要なのは「機能を追加する」という考え方で売り要素を作ってはいけないということだという。最初に説明されていたように,アクションゲームは本来受動的なものであり,プレイヤーを追い詰める状況があってはじめてさまざまな機能が意味を持つ。つまり,重要なのは,プレイヤーをとんでもない状況に追い込み,プレイヤーがとんでもない力を使ってそれを切り抜けるという絵を作ることだという。つまり,作るべきは,特殊な力ではなく,特殊な状況だというのだ。
このような状況設計は文字で伝えることが非常に難しく,ほとんど不可能であると稲葉氏は語る。それはもう「そういうもの」としかいいようのないものであるらしい。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/007.jpg) |
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/008.jpg) |
そういったこともあり,プラチナゲームズでは,ゲームデザイン部門で売り要素を決めきるようなことはしていないのだという。プログラマやVFX担当に「いい感じにしておいて」と投げると,投げられたほうは嫌でもシチュエーションを想像するしかなくて必死になって仕上げてくる。その過程でいろんな人の個性が楽しめることも同社のゲーム作りで大切なポイントだと稲葉氏は語る。
もう一つ,シリーズ作品を作るときの注意点も挙げていた。シリーズ作では前の作品でどんなことができたかをみんなが知っているため,どうしても機能中心で考えてしまいがちなのだという。すでにある機能をパワーアップさせるというやり方は分かりやすくウケもよいのだが,「根本的に間違っている」とのこと。
何度も遊べる仕組みを作る
何度も遊べるようにゲームにリプレイバリューを持たせることは重要だ。そこを中心に評価する人もいるくらいだ。ただ,苦しいことを何度もやりたがる人はいないので,リプレイバリューというものは,やっていて気持ちのいいことに結びつくものでなければならないと稲葉氏は語っている。
では,アクションゲームにおけるリプレイバリューの本質とはなにかというと,これは単純にプレイヤーのアクションスキルやテクニックが向上することにほかならないという。
あまりゲームをやることのない人にも極上の体験を提供することはもちろん重要であり,予想もつかないような状況に巻き込んでどんどん新しい体験をしてもらうような仕組みを作らなくてはならない。そのため,その局面のためだけに作られた敵やギミックが必要になってくると氏は語っていた。アクションゲームはワンオフの特注品が盛りだくさんで非常に贅沢な作りがなされているのだ。そういったものをこなしていくうちに,だんだんプレイヤーのスキルが上がっていく,アクションゲームの設計とはそのようにしなくてはならないものだと稲葉氏は説明していた。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/009.jpg) |
アクションゲームの主人公に求められるもの
純粋なアクションゲームの主人公であればあるほど,魅力的なキャラクターが必要になると稲葉氏は語る。キャラクターがスーパーパワーを発揮するには,それにふさわしい特性を持つ個性的なキャラクターが不可欠になる。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/010.jpg) |
なにをプレイヤーの体験させたいのかと,キャラクターのアートデザインは,直線状の関係にあるという。プレイヤーは自身の分身ではなく,スーパーパワーを持ったキャラクターになりきることで力を発揮するので,アクションゲームはアバターシステムなどとは相性が悪いとのこと。
一方で,主人公以外の武器やパートナーなどが成長していくようなRPG要素が強いものであればアバターシステムの相性はよい。稲葉氏が現在作成中のタイトル「Scalebound」では,ドラゴンの育成要素と,自身による高いアクション性を合わせて,純粋なアクションゲームとRPGのいいとこ取りをしているという。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/011.jpg) |
アクションゲームにストーリーは必要か
アクションゲームにとって,ストーリーとはステージの始めと終わりを行うだけのものでかまわないと,稲葉氏は述べる。「ピーチ姫がさらわれたから助けにいかなきゃ」というのは,ある意味究極のストーリーだ。プレイヤーが次の状況に飛び込むための動機を与えてくれて,コントローラを放して少し疲れた手を休める時間が取れさえすればそれで十分だとのこと。状況の変化が最優先なので,次のとんでもない状況とどういうつながり方をすればいいのか,大事なのはその部分だという。
絶対にマズいとされたのが,ストーリーから考え始めるアクションゲームで,絶対に駄作になると断言していたのが印象的だ。
ただ,かつて稲葉氏が作成した「マッドワールド」という作品は,残虐行為をすることが目的のゲームだった。プレイの動機も「もっと残虐行為をするため」に特化したゲームだ。会社を立ち上げたばかりの時期でもあり,ギスギスしていたことが原因だという。ただ,プレイヤーに残虐行為自体が動機だと気づかれることは嫌悪感を誘うため,それをごまかすためのストーリー展開に力を入れていたことはあったという。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/012.jpg) |
ゲーム体験を組み立てる「ハイレベルデザイン」とはなにか
状況の設計,システム設計,キャラクター設計と一通りの説明が終わったところで,ゲーム要素についての基本は伝わってきたのだが,今度はそれらをどう組み合わせていくかという話が行われた。
ゲーム進行の一番大きな部分で,ユーザーになにを体験させたいのかを設計する部分を,稲葉氏は(こういう用語があるのかどうか知らないがと断ったうえで)「ハイレベルデザイン」と呼んでいるという。
ゲーム全体を構成するうえで最も重要なのは「積み上げない」ことだという。1ステージめより2ステージ,さらに3ステージのほうが難度が上がるような設計は間違っていると稲葉氏は断じていた。
理由は2つあるという。遊ぶ側がどう感じるのかという問題だ。まず,感覚が麻痺する,そして疲れる。麻痺したあとに疲れた感覚しか残らないのは最悪だ。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/013.jpg) |
ではどう組み立てるのがよいかという話が始まった。まず,最初は強めの刺激が必要だという。1ステージめは強めの刺激で提供され,2ステージめはちょっと下げる,3ステージめはまた戻す。それがもたらす体験を1〜10の数値で表したものが次の写真となる。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/014.jpg) |
面白いのは,ユーザー側の体験はこれとは違った評価になることである。最初は新鮮さが加点要素となる。2ステージめはそのまま,3ステージめは最初と同じだが,体感はやや下がり,4ステージめで難度を上げると,上げた分以上に体験が強くなるのだという。
逆に積み上げ型で少しずつ難度を上げていると,慣れてくるので刺激的とは感じにくくなり,評価は上がらない。4ステージまで行くと上がるものの,前のステージより1高い刺激に対してそのまま1上がった評価に落ち着いている。合計値を見ると,投入したリソースに対しての見返りは少ない。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/015.jpg) |
このように開発コストに対しての見返りを設計していくことを,氏はハイレベルデザインと呼んでいるわけだ。
ちなみに,この先の5ステージめあたりで,一度コントローラを置かせるのか,そのまま進むのかデザインの岐路に立たされるという。次のステージで刺激を強くすれば,最後まで一気に突き進むデザインにもできる。また先が長く続くようであれば,そのあたりで手を置かせることで,疲れもなく気持ちよく中断できる。このあたりはコンテンツによって変えるべき問題だそうだ。
以上が基本的なやり方だそうだが,先日発売した「トランスフォーマーズ」では,休むことなく一気に最後まで突き進めさせるデザインが採用されているという。その方針は「密度の濃さを体験させ続ける」というもので,これはかなり欲張りなやり方であり,先ほどのようなユーザーの慣れや疲れを計算に入れたうえで刺激を与え続ける工夫がされているとのこと。かなり極端な例なので,プレイした人によってクリア時間をもの凄く短く感じる人もいれば,体験の濃さからもの凄く長い時間に感じる人もいるという。
マネは薦められないが,応用次第ではこういうこともできるというデモンストレーション的な作品と言っていいのかもしれない。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / [GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/016.jpg) |
稲葉氏は,こういった考え方はアクションゲーム以外にも応用が可能ではないかと示唆しつつ,自分達のやり方がなにかの役に立てばと聴衆に謝辞を述べて,講演を締めくくった。
わりとありがちなゲームの構成についても容赦ないダメ出しが出ていたので,会場のゲーム開発者にとって刺激的な内容だったようだ。講演後の質問には長蛇の列ができていたのが印象に残った。
- 関連タイトル:
 Scalebound
Scalebound
- この記事のURL:



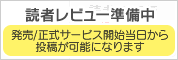







![[GDC 2016]プラチナゲームズ稲葉敦志氏が語る,アクションゲーム作りの本質に基づいた“世界で戦えるゲーム”の制作手法とは](/games/260/G026029/20160318174/TN/018.jpg)










