イベント
[GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/001.jpg) |
GDC 2016の4日め(北米時間の2016年3月17日)に登壇した,「Magic: The Gathering」(以下,M:tG)の開発者として知られるMark Rosewater氏(以下,MARO氏。M:tGコミュニティにおいて,MAROの愛称で親しまれている)も,そんな一人だ。
MARO氏は,トレーディングカードゲームというジャンルそのものを作り,世界中で大ヒットしている「Hearthstone: Heroes of Warcraft」(PC/iOS/Android)にも大きな影響を与えた,エポックメイキングなゲームデザイナーの一人である。そしてM:tGのリリース以降,20年間にわたって,M:tGだけをデザインし続けている人物でもある。
20年間,世界的に大きな人気を獲得し続けてきた作品をデザインし続けたMARO氏は,ゲームデザインに対して,どのような知見を蓄えてきたのだろうか。「Twenty Years, Twenty Lessons」と題したセッションで明かされた,氏が獲得してきた20の知見をそれぞれ見ていくことにしよう。
「マジック:ザ・ギャザリング」公式サイト
MARO氏が語る,ゲームデザインの教訓
その1:人間の本性に反するゲームデザインをすれば,敗北が待つのみ
2006年,M:tGの拡張セット「Time Spiral」において,「Suspend」というメカニズムが実装された。これは「安いコストでプレイできるが,実際にそのカードの効果を発動するには一定のターン経過が必要」という,コストと時間をトレードオフしたギミックである。
だが,このギミックを使って召喚されたクリーチャーは,M:tGのルールに従えば「Suspendが解けたターンには攻撃できない」ことになる(召喚酔いというルールが機能するため)。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/002.jpg) |
しかしながら,数ターンにわたってテーブルの上に置かれていた(召喚されていた)クリーチャーに対し,「召喚酔いだ」と言われたら,ルール的には納得できても感情的にはどうだろう?
かくしてMARO氏は,Suspendを持つクリーチャーに対し,「召喚酔いの影響を受けない」という能力を追加することにした。これによって,カードに記述されたルールは増えたが,プレイヤーはよりスムーズにゲームを楽しめるようになったのである。
このように「普通はこうだよね」という常識的な判断に逆らうようなゲームデザインは,プレイヤーに違和感を感じさせてしまう。これに対して,「ゲームに適応できないプレイヤーが悪い」と考えるのではなく,「プレイヤーに寄り添ったゲームデザインに変えよう」と考えるほうが,良い結果が得られるという。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/003.jpg) |
その2:美術は重要
「本当に面白いゲームであれば,グラフィックスはチープでもいい」というのは,しばしばゲーマーの間で口にされる。
だがMARO氏は,プレイヤーはゲームのビジュアル面(美術面)に対して「適切なクオリティ」を期待する,と指摘した。M:tGの場合,カードのアートワークという面でこの期待に応えており,囲碁のようなアブストラクトゲームにおいても碁石や碁盤は高い美術性を有している。
これはまた,機能性の側面からも考えられなばならない。人間の自然な知覚に逆らったデザインをすれば,人はそこで集中力を失い,ゲームの楽しさは損なわれてしまうからだ。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/005.jpg) |
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/006.jpg) |
その3:「共振」を利用する
プレイヤーは,特定のキーワードやジャンルなどについて,さまざまなメディアを通じて一定のイメージを有してることが多い。吸血鬼や狼男,ゾンビといえば,一般的には「ホラー」であり,そこには「恐怖」がある。
ゲームデザイナーはこうした一般的な知識やイメージに乗っかる形でゲームをデザインすれば,プレイヤーに対して調和の取れたプレイ感覚をもたらすことができる。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/007.jpg) |
その4:巨人の肩に乗る
2013年,MARO氏が拡張セット「Theros」をデザインしていたときのことだ。Therosはギリシア神話がモチーフとなっており,それを踏まえたカードがいくつも作られた。
「Akroan Horse」もそのうちの1枚で,これは「トロイの木馬」を踏まえたものだった。カードの機能も大変にそれらしく,テストプレイヤーたちはこのカードを大いに気に入った。
だが,デザインチームはこのカードをTherosの世界によりフィットさせるため,「Akroan Lion」という名前に変え,グラフィックスも差し替えた(当然,クリーチャーのタイプも「馬」から「猫」に変わった)。
その結果,テストプレイヤーは「なぜ猫が兵士トークンを生産するの?」「何が起こっているの?」と混乱してしまった。しかるにカードを再び「Akroan Horse」に戻すと,混乱は収束したのである。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/009.jpg) |
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/010.jpg) |
このように,多くの人が知っている概念や名前を利用することで,ゲームに対するプレイヤーの理解を深めることができる。
M:tGで言えば,「飛行」というクリーチャー能力もこの類例だ。「飛行」を持つクリーチャーは,「飛行」を持つクリーチャーでしか迎撃できない。つまり,「飛行」しているクリーチャーは,「飛行」していないクリーチャーの上空を通過できるというわけだ。
言葉遣いや固有名詞は,一見するとフレーバーにしか見えないが,ゲームをより楽しめるものにするにあたって,非常に重要な役割を果たしている。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/011.jpg) |
その5:「興味深い」と「楽しい」を混同しない
M:tGには,カードアドバンテージという理論がある。簡単に言えば,「たくさんカードを持っているほうが有利」というものだ。これは,M:tGのゲームロジックを支える根底的な理論の一つである。
しかし,2001年にMARO氏がデザインした拡張セット「Odyssey」では,「Threshold」というメカニズムが導入されている。これは,「墓地(捨て札置き場)に7枚以上カードがあると,特別な効果を発揮する」というもの。このメカニズムと,「手札からカードを好きなだけ捨てられる」というメカニズムを持ったカードを同時に利用することで,プレイヤーは迅速に強力なカードにアクセスできるようになる。
でも,手札を捨ててしまっているから,カードアドバンテージ的には不利だ。なんと,すばらしいジレンマだろうか!
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/012.jpg) |
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/013.jpg) |
しかし,実際に拡張セットをリリースしてみると,このジレンマは不評だった。理論上ではバランスも取れていて,知的で興味深いジレンマになっているのだが,それが必ずしもプレイヤーに「楽しさ」を感じさせるわけではないのだ。
これについてMARO氏は,プレイヤーに「楽しさ」「満足感」を与えたいのであれば,知的なレイヤーに働きかけるよりも,情緒的なレイヤーに働きかけたほうが,より良い結果が生まれやすいと語った。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/014.jpg) |
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/015.jpg) |
その6:そのゲームを通じて,プレイヤーの間にかき立てようとする感情が何であるかを意識する
2011年にリリースされた「Innistrad」という拡張セットのテーマはホラーだった。つまり,プレイヤーに感じてほしい感情は「恐怖」である。
そして,これに基づき,「Innistrad」ではホラーがモチーフとなったカードがたくさん作られ,多くのプレイヤーの共感を得ることに成功した。また,新たに導入されたゲームシステムも,ホラーの王道を感じさせるものだった。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/016.jpg) |
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/017.jpg) |
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/018.jpg) |
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/019.jpg) |
これについてMARO氏は,映画やドラマの制作において鉄則とされる言葉を引用した。「映画全体より価値のある1シーンなど存在せず,1シーンよりも価値のあるセリフ1行など存在しない」。つまり,どんなにすばらしく思えるシーンであったとしても,それが映画全体に寄与しないのであれば,そのシーンはカットすべきなのだ。
同様にゲームシステムにおいても,それがどんなにすばらしいシステムであったとしても,プレイヤーが楽しいと感じられない,または楽しさと関係のないものであるなら,それは放棄したほうがいいのである。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/020.jpg) |
その7:ゲームを「プレイヤー自身のもの」とせよ
M:tGのアートワークにおいて,Christopher Rush氏(故人)が果たした功績は極めて大きい。だが彼のセンスは,アートワーク以外でも発揮されていた。
かつてChristopher Rush氏は,M:tGにおける最も基本的なリソースである「土地カード」に対し,「もっと絵を大きくしてもいいんじゃないか?」と提案したという。その場では否定された意見だったが,MARO氏は2004年の「Unhinged」というジョークカード専用の拡張セットでこの提案を採用。土地カードとして,大きな絵が描かれたカードがリリースされ,これは大きな反響を得た。かくして2009年,「Zendikar」拡張セットにおいて,「Unhinged」スタイルの土地カードが正式採用される運びとなった。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/021.jpg) |
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/022.jpg) |
想像以上に,この効果は大きかった。これまでも土地カード(基本地形は5種類)には,それぞれのタイプに複数のアートワークが用意されていたが,絵が大きくなることでその「違い」が明確になったのである。
これにより,プレイヤーは特定の絵柄の土地カードで統一したり,特別なカードセットの土地カードを使ったりという形で,より「自分らしいデッキ」を作りやすくなった。
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/023.jpg) |
この「自分らしい」という感覚には,別の意味もある。
大まかに言うと,人間の脳は「自分が知っている事物」について,その価値を保証する傾向にある。事実,スーパーマーケットで多数のシリアルが並んでいる棚から1つを選ぶとき,ほとんどの客は「自分が知っている商品」を「良い商品」として選択するのである。
一方で,「自分らしさ」=「自分ならではの選択の結果」という要素がゲームに加わることで,プレイヤーは「そのゲームを自分はよく知っている」という感覚を深める(もちろん,選択を強制してはならないが)。そして,その感覚はプレイヤーに対して「そのゲームは良いものだ」という感覚を醸造する。
![画像ギャラリー No.024のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/024.jpg) |
その8:プレイヤーは細部に対して愛情を抱く
「Return to Ravnica」ブロックに属する拡張セット「Gatecrash」には,「Totally Lost」というカードが存在する。これ自体はさほど強力なカードではないが,カードに描かれた「Fblthp」というキャラクターは,なぜかM:tGコミュニティにおいて爆発的な人気を博し,さまざまなファンアートやコラージュが作られた。
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/025.jpg) |
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/026.jpg) |
![画像ギャラリー No.027のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/027.jpg) |
![画像ギャラリー No.028のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/028.jpg) |
![画像ギャラリー No.031のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/031.jpg) |
![画像ギャラリー No.030のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/030.jpg) |
![画像ギャラリー No.029のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/029.jpg) |
![画像ギャラリー No.032のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/032.jpg) |
![画像ギャラリー No.033のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/033.jpg) |
![画像ギャラリー No.034のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/034.jpg) |
![画像ギャラリー No.035のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/035.jpg) |
![画像ギャラリー No.036のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/036.jpg) |
![画像ギャラリー No.037のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/037.jpg) |
![画像ギャラリー No.038のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/038.jpg) |
![画像ギャラリー No.039のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/039.jpg) |
個々の細かな設定そのものが,必ずしもプレイヤーのゲームに対する愛情につながるわけではない。だが,こうした細部はプレイヤーがゲームに愛情を感じる発端となることはある。Fblthpさんは,まさにそのケースだ。
その9:プレイヤーに所有感を与えよ
M:tGには,さまざまな「フォーマット」がある。フォーマットとは「どんなカードを使用していいのか」(これが主)から「どのようにプレイするのか」までを包括する,メタルールの一種だ。
いま最も人気のあるフォーマットの一つが,「Commander」と呼ばれるものだ。そして,このフォーマットはM:tGを制作しているWizards of the Coastが作ったものではない。
Commanderフォーマットを作り上げたのは,M:tGの公式トーナメントを支える重要な裏方である審判(ジャッジ)達だった。彼らは日がな一日(ときには数日に渡って),審判としてM:tGの勝負を見守ることになるため,仕事を終えたあとは「M:tGが遊びたくてしかたがない」心境に陥る。そんな彼らが,自分達の最も楽しめるフォーマットとして作り上げたのがCommanderだというわけだ。
![画像ギャラリー No.040のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/040.jpg) |
![画像ギャラリー No.041のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/041.jpg) |
![画像ギャラリー No.042のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/042.jpg) |
![画像ギャラリー No.043のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/043.jpg) |
![画像ギャラリー No.044のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/044.jpg) |
このようにゲームそのものをカスタマイズできるということは,プレイヤーに対して「このゲームの所有者は自分」という感覚を与える。
M:tGの場合,当然ながら「デッキを作る」という作業もまた,ゲームをカスタマイズすることにほかならない。膨大なカードプールから,自分なりのセオリーや好みでカードを選び,1つのデッキを作り上げていくという行為は,単に「デッキを作っている」のではなく,「自分のデッキを作る」という行為だ。それはもはや,プレイヤーにとって,自分自身を表現することですらあるのだろう。
![画像ギャラリー No.045のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/045.jpg) |
その10:プレイヤーに探索の余地を与えよ
M:tGには「コンボ」と呼ばれる概念がある。これは格闘ゲームのコンボとは異なり,複数のカードを組み合わせることで,カード単体では到達できない強烈な効果を発揮させるという考え方だ。
20年に及ぶM:tGの歴史と戦略の中で,何度も何度も強力無比なコンボが出現し,トーナメントを荒らしていった。とくに「極めて強烈だが,発見者がほとんどいない奇抜な組み合わせ」で構成されるコンボを中心に構築されたデッキは,日本において「地雷デッキ」と呼ばれ,これまた何度もトーナメントを震撼させた。
このようなコンボ(あるいは地雷デッキ)について,MARO氏は「プレイヤー自身が発見できるということに,大きな意義がある」と語る。
![画像ギャラリー No.046のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/046.jpg) |
かつてテレビドラマの脚本家であったMARO氏は,脚本の売り込みにおいて,「相手に対して話すのではなく,相手と一緒に話をしろ」と教えられたという。そうして,買い手側が価値や可能性を「自分で発見した」とき,売買が成立するというわけだ。
M:tGもこれと同じく,プレイヤーが自分自身で発見したコンボや戦略は,プレイヤーの愛着を生む。ゲームにその手がかりや可能性を散りばめるとしても,それを発見するのはプレイヤー自身でなくてはならないのである。
![画像ギャラリー No.047のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/047.jpg) |
その11:「好き」をどんなに集めてもゲームは失敗する。「愛」を集めよ
MARO氏は,M:tGに存在するレアカードについて,Wizards of the Coastの社員にアンケートをとったことがあるという。その結果を今後の開発に活かしていこう,という腹である。
だが,そのアンケートに記述された評価を「どう評価するのか」という問題が発生する。10段階でカードが評価されるのだが,誰もが「7」をつけるカードと,半数は「1」「2」,残りの半数は「9」「10」をつけるカードでは,どちらが「良いカード」なのだろうか。
![画像ギャラリー No.048のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/048.jpg) |
正解は,後者である。
大事なのは,プレイヤーに「深い感情を抱かせる」ことだ。誰もが「悪くないね。僕は好きだよ」と思うようなものでは,人間の感情を本当に動かすことはできない。たとえ憎悪されることがあったとしても,LikeではなくLoveを惹起しなくてはならないのである。
それゆえ,「否定的な反応を恐れてはならない。それよりも,どうしたら“強い”感情を引き起こせるかで悩むべきだ」とMARO氏は指摘する。
その12:実力を見せつけるためにゲームをデザインするな
M:tGには,「Planeswalker」という種類のカードが存在する。とても人気のあるカードタイプで,新しいセットが作られるときには「次はどんなPlaneswalkerが来るのだろう?」と期待が高まる。
だが,Innistradブロックの拡張セット「Avacyn Restored」において,事件は発生した。「Tibalt, the Fiend-Blooded」というPlaneswalkerを導入したのである。
Tibaltの登場まで,Planeswalkerは最低でも4マナ(リソース4つ)が必要なカードだった。だが,Tibaltはわずか2マナで召喚できる。これは,MARO氏らデザインチームにとって,「低コストで召喚できるPlaneswalkerだってデザインできる」という自負の現れであったという。
![画像ギャラリー No.049のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/049.jpg) |
しかし,プレイヤーの評価は辛口だった。実際,Tibaltは使いにくいPlaneswalkerであり,しかもレアスロットに入るカードだったため,多くのプレイヤーは「こんなレアは引きたくなかった」と嘆くことになったのだ。
「ゲームデザイナーとしてエゴは大事だ」とMARO氏は語る。「だが,ゲームデザイナーが仕える相手はプレイヤーであり,自分が楽しむためにゲームをデザインしてはならない」のである。
その13:ゲームを楽しむことによって,戦略的にも優位に立てるようにデザインせよ
前述したとおり,Unhingedはジョークカードだけを集めた拡張セットである。したがって,公式戦では基本地形カードくらいしか使えない。
Unhingedでは,「Gotcha」と命名されたゲームシステムが採用されていた。これは,対戦相手が特定の言葉を口にしたり,動作をしたりしたら,「Gotcha!」と叫んで発動させるものである。なるほど,ジョークセットらしい,ゲームを愉快にしそうな能力と言える。
だが,実際に「Gotcha!」をたくさん含んだデッキで対戦すると,プレイヤーにとって最良の選択肢は「勝負の間,一切のムダ口を叩かず,姿勢を崩さず,ただ黙々とプレイし続ける」ことだ。いかにジョークカードとはいえ,これは到底,楽しい体験にはならない。
![画像ギャラリー No.050のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/050.jpg) |
ゲームのルールとは,プレイヤーに対するデザイナーからの「約束」とも言える。デザイナーは「このような選択肢の範囲内で,ルールに従って行動し,勝利を目指せば,たとえ負けたとしても楽しい体験ができます」という提案をしているのだ。
それゆえ,その約束を守ったのに楽しい体験が得られなかったとなれば,プレイヤーが怒るのは当然と言えるだろう。
もちろんプレイヤーは,デザイナーが意図しないところに「楽しさ」を見出すこともある。それでも,デザイナーはきちんと「楽しさ」をデザインし,それが勝利への道と合致するようにしなくてはならないのだ。
![画像ギャラリー No.051のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/051.jpg) |
その14:ストレートすぎる表現を恐れるな
ゲームデザイナーを含むアーティストというものは,繊細で緻密な表現を好むことが多い。だが,繊細さが役に立たない状況というものは存在し,人間はときに「どう見たって明らか」なことを見落としたりする。
実際,1999年に発売された「Mercadian Masks」では,ブロック特有の新システムに対して,これといった命名をしなかった。その結果,ユーザーからは「どうしてMercadian Masksには新メカニズムがないのか?」という質問が飛び出したという。
![画像ギャラリー No.052のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/052.jpg) |
この「ときには露骨に表現したほうがいい」という方針は,もっと掘り下げることもできる。
たとえば「非常にコストパフォーマンスの高いモンスターで,新メカニズムも凶悪」といったカードの場合,あえて「毎ターン必ず攻撃すること」というルールを付加する。
すると,最初はルールに従って攻撃を行ったプレイヤーが,その強さを実感したあとでは,喜んで攻撃しにいくようになるという。「攻撃してもいいんだよ? 強いんだよ?」とほのめかすのではなく,「攻撃しろ! 強いんだから!」とストレートに訴えることは,ときに有効なのだ。
![画像ギャラリー No.053のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/053.jpg) |
その15:ターゲットを絞り,そのためのコンテンツを作れ
M:tGは多数のプレイヤーを有するゲームであり,プレイヤーによってゲームの楽しみ方は異なる。ここにおいて「すべてのプレイヤーが満足できるカードを作ろう」などと考えてしまうと,結果的に誰にとっても不満足なカードができてしまうことがある。
![画像ギャラリー No.054のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/054.jpg) |
![画像ギャラリー No.055のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/055.jpg) |
M:tGの場合,カードは無数にある。そのうちの1枚を特定のターゲットに絞ったカードにしても,それだけでターゲット以外をないがしろにしたということにはならない。むしろ,ターゲットをきちんと絞り,そのターゲットが望むカードへと仕上げることによって,トータルでのゲーム体験を向上させることができる。
その16:プレイヤーに挑戦することを恐れるな。退屈させることこそ恐れよ。
2000年に発売された「Invasion」ブロックには,奇妙なカードが収録されていた。これらは分割カードと呼ばれ,1枚のカードレイアウトの中に2枚の小さなカードが書き込まれている。プレイヤーはどちらかの機能を使うことができた。
![画像ギャラリー No.057のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/057.jpg) |
![画像ギャラリー No.058のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/058.jpg) |
分割カードというアイデアに対して,Wizards of the Coastの上層部(M:tGのメインデザイナー,Richard Garfield氏を含む)の3名は「良いアイデアだ」と支持した。
だが,ほかの社員は「こんなのはM:tGのカードではない」と,猛反対したというのである。しかしながら,分割カードはリリースされるや否や,ユーザーから大いに支持されることとなった。
このような経験は決して初めてではない,MARO氏は語る。そして,実はより深刻な問題の顕現でもある。
MARO氏によると「20年間,Wizards of the Coastに勤務してきたが,何か新しいことに挑戦しようとすると,『無理だ』『リスキーだ』『ゲームを壊す』と反対する意見が必ず一斉に湧き上がった」という。だが,不思議なことに「ゲームが退屈になりそうな要素については,誰も批判しない」。
これについて,MARO氏は「プレイヤーを退屈させることより,プレイヤーに挑戦することのほうを,より恐れる」と分析する。
肝心のプレイヤー側から見ると,その評価はまるっきり逆だ。プレイヤーは挑戦を評価し,たとえそれが失敗に終わったとしても,「次は何をやってくれるんだろう?」と期待を抱く。一方で,退屈な思いをしたが最後,最悪の場合はそこでゲームを辞めてしまう。「最大のリスクとは,リスクをまったく取らないこと」なのだ。
![画像ギャラリー No.059のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/059.jpg) |
![画像ギャラリー No.060のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/060.jpg) |
その17:巨大な変革のために,すべてを変える必要はない
2000年の「Invasion」ブロックでは,複数色のマナ(複数のリソース)を使ったカード(およびシステム)というものが1つのテーマとなっており,プレイヤーはこれを大いに評価した。
そして2005年,「Ravnica」ブロックにおいて,再び多色マナをブロックのテーマにしようということになった。
ここで,一つの問題が発生する。どうしたら「Ravnica」を「Invasion」と差別化できるのだろうか。
MARO氏は,M:tGの持つ5つの色に注目し,その組み合わせを増やすのではなく,減らす方向でデザインを進めた。「Invasion」ブロックにおいては最大5色の複合まであった多色カードを,完全に2色(つまり最小の多色)へと絞り込んだのである。
5色のうち2色を選んだ組み合わせは,全部で10とおりだ。それらの組み合わせに対し,MARO氏はそれぞれ「ギルド」を設定した。これによって,Ravnicaの世界はこれまでにない,高い人気を誇るようになったのである。
![画像ギャラリー No.061のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/061.jpg) |
![画像ギャラリー No.062のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/062.jpg) |
ゲームをデザインしていると,どうしても仕様は増えていく。デザイナーとしては,仕様を増やせば増やすほど,「ウケる」層が増えるような気がするので,なかなか歯止めをかけるのは難しい。だが,そうして足し算を繰り返した先にあるのは,ゲームとしての破綻であり,プレイヤーはそれを見て戸惑うことしかできない。
MARO氏は「どれくらい仕様を足さねばならないのか」と考えるのではなく,「どれくらい何も足さずに済むのか」と考えるべきだと語った。
![画像ギャラリー No.063のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/063.jpg) |
![画像ギャラリー No.064のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/064.jpg) |
その18:制限があることで,クリエイティビティが生まれる
MARO氏は開発者ブログを書いているが,テーマを決めて書く期間と,テーマを決めずに書く期間があるという。このうち,書きやすいのは後者の期間だという。
また,ゲームデザインにおいても,テーマを決めてカードデザインしていくときと,とくにテーマを決めずにデザインしていくことがあり,この場合でも作りやすいのは後者だ。
![画像ギャラリー No.065のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/065.jpg) |
![画像ギャラリー No.066のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/066.jpg) |
だが,ことクリエイティビティという観点に立つと,「テーマが決まっている」といった形で制限が存在することは,より良いクリエイティブに寄与するという。
というのも,人間は選択肢が多ければ多いほど,自分がかつて成功した選択肢を,無意識のうちに選んでしまうからだ。これはこれで「成功する確率」としては望ましいかもしれないが,「似たようなものが作られる」という失敗に陥る危険性も高まる。
ゆえに,まだスタート地点として選んだことのないところを起点とすることほうが,新しい結果を生み出せる可能性も高くなるのである。
その19:ファンは問題を探り当てる達人だが,解決法はロクなものを提供してくれない
MARO氏は,Tumblrで6万4000件近いエントリーを書いており,6万件以上のコメントに返信している。これだけでも莫大な数字だが,オフラインの場においても氏は質疑応答に細かく応えている。そのトータルがどれくらいになるかは想像もできない。
![画像ギャラリー No.067のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/067.jpg) |
![画像ギャラリー No.068のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/068.jpg) |
その経験を踏まえると,ファンはゲームに何か問題があること,またどんな問題があるかという分析においてはデザイナー以上の能力を持つ。しかし,その問題をどう解決すべきかという点については,まるで参考にならないという。
それゆえ,問題点を探り当てる手段として,ファンの声に耳を傾けるというのは非常に重要であり,やるべき。だが,解決策まで彼らに依存してしまうと,非常に良くないことが起こる。
その20:すべての教訓はリンクしている
これまでの19の教訓は,どこかでつながっている。だから,どれか1つにすがるのではなく,全体を見て組み合わせて考えていくべきだ。
実際,今回の講演に向けて,MARO氏は「20年かけて知った,1つの非常に複雑で相互連携した総論的ゲームデザイン論」というタイトルを考えていたという(冗談かもしれないが)。それくらい,これらの教訓は「1つ」のものなのだ。
![画像ギャラリー No.069のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/069.jpg) |
MARO氏が列挙した20(19+1)の教訓の中には,「同じことを違う言葉で言っているのでは?」と思うものもあるが,その多くは非常に具体的で納得できる。デジタルであれ,アナログであれ,ゲーム制作を志す人にとっては,MARO氏の教訓を座右の銘とする価値があるだろう。
最後に,MARO氏は教訓を箇条書きにした画像を見せてくれた。その写真をもって,本稿の結びとしたい。
![画像ギャラリー No.070のサムネイル画像 / [GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/070.jpg) |
4Gamer GDC 2016関連記事一覧
- 関連タイトル:
 マジック:ザ・ギャザリング
マジック:ザ・ギャザリング
- この記事のURL:


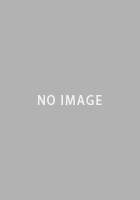
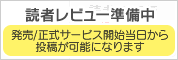







![[GDC 2016]「Magic: The Gathering」を20年間デザインしてきたMark Rosewater氏が,自身の経験から得た“20の教訓”を語る](/games/136/G013687/20160318166/TN/056.jpg)










