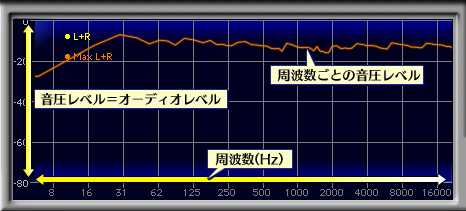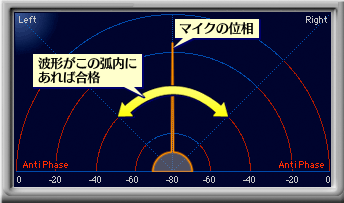レビュー
追加ドライバなしでバーチャルサラウンドを実現するヘッドセット
SteelSeries Siberia v2 Full-size Headset USB
 |
そんなSiberiaシリーズの最新ヘッドセットとして登場したのが,その名もズバリ「SteelSeries Siberia v2 Full-size Headset」(以下,Siberia v2)である。「Icemat Siberia」(現「SteelSeries Siberia」,以下 初代Siberia)として2005年春頃に国内販売された初代と同じ,ヘッドバンド型を採用する“v2”は,白基調のアナログ接続モデルと,黒基調のアナログ接続ヘッドセットとUSBサウンドデバイスのセットモデル「SteelSeries Siberia v2 Full-size Headset USB」が用意されるが,今回は後者を取り上げたい。アナログ接続ともども,その実力を検証してみよう。
なお,USBサウンドデバイスが付属するのか否かと,本体の色,そして価格以外,アナログ接続専用モデルとアナログ&USB両対応モデルに違いはないため,本稿では以下,明示的に書き分ける必要のある局面を除き,両モデルをまとめてSiberia v2と呼ぶ。この点はあらかじめお断りしておきたい。
マイクを内蔵も,シルエットは従来製品を踏襲
軽い筐体に50mmドライバー搭載
 |
ブームは,Siberia Neckbandと同じなのではないかと思われるが,不要なときにしまっておけるうえ,蛇腹仕様のため自在に配置できる。しかも配置後の“遊び”が少ないため,狙った場所にぴたりとポインティング可能と,完成度はかなり高い。
 |
 |
 |
いきなりマイクの話からになったが,いったん目線を引いて,全体を概観しておこう。
冒頭でも簡単に紹介したが,Siberia v2は,アナログ接続専用モデルが,白を基調としつつ黒をあしらった外観,そして,アナログ接続ヘッドセットとUSBサウンドデバイスのセットモデルが,光沢感のある黒基調のカラーリングとなっている。
 |
ケーブルを含む重量は実測256gで,ケーブルを重量計からどかした参考値では232〜234g。可動部分の大部分がプラスチック製のためか,見た目に反して相当に軽い印象だ。
さて,軽いということは,
- ヘッドセットの重みを感じることなくゲームに集中できる
- 軽すぎて,ゲーム中に頭を激しく動かすとズリ落ちてしまう
 |
一方,スポンジなどが入っておらず,スエード生地が頭頂部と直接触れるタイプのヘッドバンドは,テグス(≒釣り糸)のような材質の糸でエンクロージャとつながる仕様になっているのだが,この仕様ゆえか,横方向の締め付けがあまり強くない。糸自体は丈夫そうで,そこに問題は感じないものの,筆者が装着すると,耳の下側部分で,エンクロージャと耳の間に“あそび”ができてしまう。
 |
 |
 |
密閉型であそびがあるというのは,音漏れが発生するというのと同義であり,低域の周波数特性に大きな負の影響が生じるということでもある。もちろん,頭の形状にもよるので,全員が全員,筆者と同じ体験をするとは限らないが,最初から締め付けがここまで弱いというのは心許ない。もう少し強ければ解決しただけに,残念なポイントである。
 |
 |
 |
本体から伸びるケーブルには,インラインのボリュームコントローラ兼スライド式マイクミュートスイッチが用意されている。スライドスイッチはそこそこ大きめなのだが,多少硬めで,しかも爪を引っかけるような突起がないため,少々扱いづらい。
 3.5mm径のミニピンは,緑がヘッドフォン端子,ピンクがマイク端子といった具合に,リングの色で用途を判別できる |
 SteelSeriesロゴ入りインラインコントローラ。ボリュームノブも小さい。人によっては,こちらも使いづらいと思うかも |
USBサウンドデバイスはDSP内蔵か
追加ドライバなしでバーチャルサラウンドを実現
 |
ただ,Siberia v2の場合,それだけに留まらない。USBサウンドデバイスは,単体で,バーチャル7.1chサラウンドサウンド出力に対応している。要するに,Creative Technologyの「CMSS-3Dheadphone」や,Dolby Laboratoriesの「Dolby Virtual Headphone」のようなバーチャルヘッドフォン機能を実現できるのだ。しかも,追加のドライバなしで。
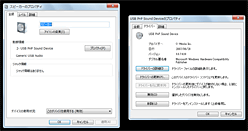 |
従来的な“USBサウンドコントローラ”だと,このような機能はCPUによるソフトウェア処理が必要で,いきおい,追加のドライバソフトウェアなどが必要だった。それを考えると,Siberia v2のUSBサウンドデバイスでは,DSP(Digital Signal Processor)か,それに近い機能が実装されたと見るべきではなかろうか。
 |
いずれも電子式スイッチとなるボタンは4個で,うち二つがボリュームの引き上げ/引き下げ,残る二つがマイクミュートと,マイクミュート解除用。ノートPCや,手元にUSBインタフェースを引き出せるタイプのデスクトップPCだと,場合によっては手元で制御できそうなのだが,残念ながら,ボタンが硬い,ミュートが有効にならないなど,使い勝手はアナログヘッドセット側のコントローラに輪をかけて悪い。総じてSiberia v2のリモコンは,今ひとつの完成度とまとめざるを得ないだろう。
パワー感を欠くが,HiFi寄りのチューニング
ゲームでは迫力の重低域とくっきりした高域が印象的
筆者のヘッドセットレビューでは毎回お断りしているが,テストは,ヘッドフォン部を試聴で,マイク入力は波形測定と入力した音声の試聴による二本立てで行う。
ヘッドフォン出力品質のテストに用いているのは,基本的に,「iTunes」によるステレオ音楽ファイルの再生と,「Call of Duty 4: Modern Warfare」(以下,Call of Duty 4)マルチプレイのリプレイ再生。比較対象として,AKG製のヘッドフォン「K240」を用意しているので,本製品との比較を交えながら述べていきたい。
一方,波形測定方法の説明は長くなることから,本稿の最後に別途まとめてあるので,興味のある人は参考にしてほしい。基本的には,本文を読み進めるだけで理解できるよう,配慮しているつもりだ。
今回のテスト環境は下に表で示したとおりとなる。USBサウンドデバイスは,マザーボードのUSB端子と直接接続した。
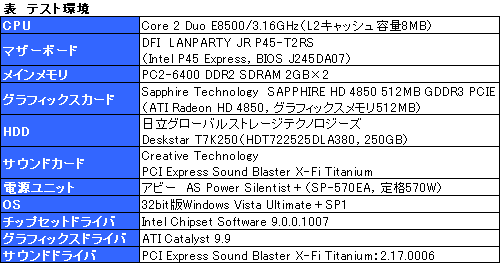 |
 |
まず,Siberia V2を「PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium」(以下,X-Fi Titanium)とアナログ接続したときの音質傾向だが,Siberia Neckbandのような“低強高弱”ではない。50mmスピーカードライバーの再生特性が貢献しているのかどうか,重低域が強く再現されるのはSiberia Neckbandと同様だが,おそらく4kHzと思われる高域の伸びも強い。そのため,左右チャネルの分離度が高い印象だ。中低域の帯域は抑え気味なので,いわゆるパワー感は欠くものの,その分,すっきりした音質傾向になっている。
音楽の場合,中低域(250Hz〜750Hz付近)の強い,一般的な楽曲を聴くと,やはりパワー感の不足は気になる。ただ,“ドンシャリ”の“シャリ”(=高域)が強い,Sennheiser(ゼンハイザー)製イヤフォンのような性格もあって,トランジェント(※シンバルやピアノのようにアタックの強い音)はくっきり聞こえる。
一方,シンセベースなど,重低域の多く含まれた楽曲を聴くと,印象ががらりと変わる。びっくりするくらい重低域がドーンと出てくるのだ。K240と比べても,重低音と高音の再生能力は随分と高い。
ただ,K240にある「適度な中低域」が抑えられているため,楽曲を聴いたときのパワー感はK240に譲る点も指摘しておく必要がありそうだ。
全体の音量は,大きすぎも小さすぎもせず,ほどほど。ツルツル(=ハイインピーダンス)とザラザラ(=ローインピーダンス)の音,どちらに近いかというと,若干ツルツル寄りだが,味も素っ気もないほどツルツルというわけではなく,ギリギリの線で踏みとどまっているように聞こえる。
なお,USBサウンドデバイスを経由させても,音質傾向は基本的に同じだが,重低域〜低域はやや抑えられる。ただここは逆に,「アナログ接続時は,低域を強く再生するX-Fi Titaniumに引っ張られている」と表現したほうが,より正確だろう。
全体として,パワー感が欲しい人,とくに,中低域のパワー感を重視するダンスミュージックなどを好んで聴く人だと,物足りなさを覚えるはずだが,バランスよく音楽を聴くタイプの人ならアリといえる。基本的には,ジャンルをあまり問わない,よいヘッドフォン品質だ。
 |
 |
これはおそらく,すっきりした中低域と,十分に再生できている重低域の賜物だ。
高域の伸びは,Call of Duty 4でも十分強く,サラウンド感はしっかり感じられる。一方,2〜3kHz付近の,強すぎると耳が痛くなる帯域はそこそこ抑えられているので,よほど音量を上げすぎない限りは,「高域だけ強くてつらい」ということもない。ほかの用途にも利用できる製品シリーズとして訴求されてはいるものの,基本はしっかりとゲーマー向けモデルであると述べてよさそうである。
次にUSB接続時だが,やはりゲームサウンドにおいても,傾向そのものはアナログ接続時と同じ。前述のとおり,X-Fi Titaniumの重低域出力が相対的に強いこともあって,X-Fi Titanium+Siberia v2の組み合わせと比べると重低域が多少弱く感じられるが,実際に,爆発音や,瓦礫の崩れる音などで聞き比べる限り,ほとんど気にならないレベルの差でしかない。
 |
驚いたのはそのサラウンド感で,結論から先に述べると,相当に優秀だ。テストの前は,あくまでも「バーチャルサラウンドあります」的なオマケだと思っていたのだが,いい意味で,その予想は完全に裏切られた。
イメージとしては,CMSS-3DheadphoneよりはDolby Virtual Headphoneに近い印象を受けるが,とくに秀逸なのは横から後方にかけての定位感。背後でキャラクターが走っていたり,何か物音がしたりという状況が,とても分かりやすい。横方向への広がりは,CMSS-3Dheadphoneと比べて明らかに深いうえ,CMSS-3Dheadphoneだと,どうしても若干,変調した音になってしまうところでも,Siberia v2では,クリアな音質傾向を保ったままになる。
ただ,CMSS-3Dheadphoneが得意とする正面の定位感は今ひとつで,プレイヤーキャラクターが銃を撃ったときなどは,音が目の前に定位せず,前方で広がって聞こえてしまう。照準を中心に,前方−30〜+30°の間で鳴っているような印象もある。
また,いくつか試した限り,どうやらDirectSoundは強制的にバーチャルサラウンド処理されるようで,たとえば「ファイナルファンタジーXI」など,2chステレオサウンドを採用したタイトルで使うと,センター成分がいなくなって,音が左右に妙な広がり方をしてしまう。縦スクロールのシューティングゲームなどでも同じような結果だったので,これは一部の人にとって致命的な「仕様」だと指摘しておきたい。
マイクは高域がかなり強めで
若干“鼻づまり”気味の音質
続いてはマイクである。仕様上の周波数特性は50Hz〜16kHzとなるマイクだが,X-Fi Titaniumのマイク入力端子(=「FlexiJack」のマイクモード)だと,大きな落ち込みは確かに60Hz付近より下と,12kHz以上で発生しているため,まずまず仕様どおりと述べていい。また,1.4kHz付近の落ち込みは,スピーカーのクロスオーバーポイントによるものなので無視できるが,それにしても2〜10kHzの帯域が極端に高い。その差はざっと15dBほどだ。
この「高域の妙な強さ」が音にどう影響するのか,実際に聞いてみると,高域が強いためクリアなのはいいとして,ちょっと鼻をつまんだような音に聞こえる。実用レベルの音ではあるので,気にならない人が大半だとは思われるが,そういう傾向であることは押さえておきたい。
なお,位相はまったくズレていない。仕様上,単一指向性マイク×1なので,当然といえば当然か。とくにノイズリダクション機能は採用されていないようなので,「指向性を狭めてノイズを減らす」という,シンプルかつ伝統的な収録技術が採用されているとまとめられよう。
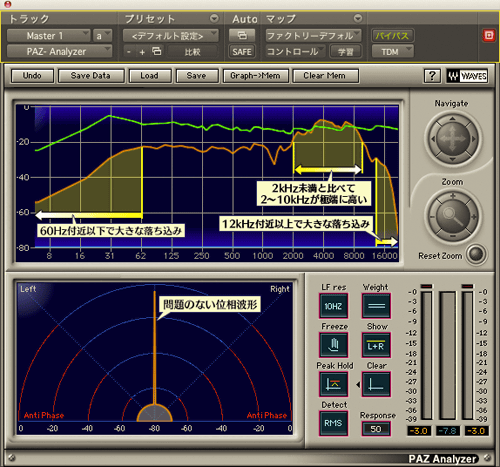 |
一方,USBサウンドデバイスを介すと,ずいぶん異なる印象の特性が得られる。ヘッドセット本体の接続インタフェースはあくまでもアナログなので,USBサウンドデバイスの入力品質が高いのか,付属品ということで最適化されているのかまでは分からないが,いずれにせよ,2〜12kHz付近の山はそのまま残っているものの,それ以外の帯域との差は,10dB程度かそれ未満に抑えられている。上で示したアナログ接続時の波形を,縦方向に圧縮したようなイメージだ。
この「縦方向に圧縮された感じ」が何を意味するかだが,一つ考えられるのは,「Sensitivity」(センシティビティ)と呼ばれる入力感度を最適化することで,USB接続時にダイナミックレンジをうまく圧縮している可能性だ。理論的には,ダイナミクス調整をUSBサウンドデバイス側で行っている可能性もゼロではないが,実装コスト的にありえないと思う。
アナログ接続時との聴感上の違いは,グラフほどはない。高域が強めでクリアな傾向も,若干鼻づまり気味というのは同じだ。周波数特性のピーク帯域に差がない以上,当然といえば当然の結果である。
なお,USBサウンドデバイスだとときおり感じられる入力の遅延は,少なくとも目立ったレベルでは感じられなかった。
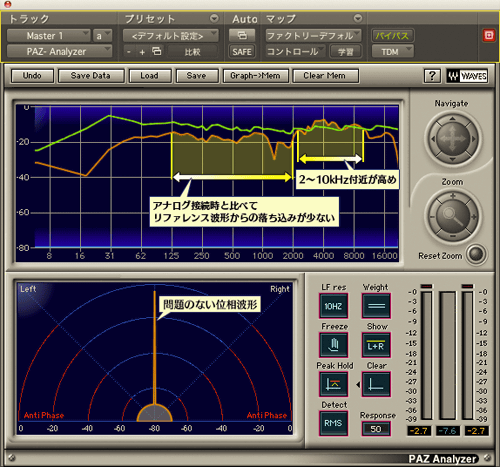 |
「USBサウンドデバイス付属アナログヘッドセット」
の概念を変える製品。トレンドが変わるか?
以上,Siberia v2をテストしてきたわけだが,最大の収穫は,付属のUSBサウンドデバイスが,CMSS-3Dheadphoneと比べても遜色のない品質のバーチャルサラウンドアルゴリズムを搭載していた点だろう。
ベースモデルとしてアナログ接続タイプが用意され,USBサウンドデバイス付属モデルも用意されるというヘッドセット製品の場合,従来は,「どうしてもUSB接続で利用したい」といった理由がない限り,後者を選ぶ必要はなかったが,その意味でSiberia v2は画期的な製品といえる。バーチャルサラウンド出力に対応したサウンドカードを別途用意しなくても,ただUSB接続するだけでバーチャルサラウンドサウンド環境が手に入るというのは,やはりインパクトが大きい。
 |
ヘッドセット本体に関してまとめると,「耳が痛くならない程度に,高域をしっかり出していく」という,至極常識的な線――というか,西洋人や日本人が好むサウンド――を踏襲し,万人に勧めやすい品質に仕上がっている点は,素直に歓迎したいところ。重低域はしっかりと存在し,同時に,高域がぼやけたりすることもないので,不満は感じにくいはずだ。
というわけで,アナログ接続モデルは,X-Fi Titaniumなど,バーチャルサラウンドサウンド環境をすでに持っていて,すっきりしたサウンドを手に入れたい人,そしてUSB接続モデルは,3Dサラウンドサウンド環境を手間なく構築したい人向けとまとめられそうだ。
ただし,ヘッドバンド部の締め付けが弱いのは懸念材料として残るので,できれば一度,展示機の置かれている店頭で試してみることを勧めたい。
……ところで,サウンドデザイナーという職業柄,業界内の情報を耳にすることが多いのだが,確度の高い情報筋によれば,Intelは最近,CODECのメーカーに対し,「サウンドCODECに,DSP機能を内蔵する」方向の設計ガイドラインを提示したようだ。おそらくSiberia v2は,SteelSeries独自の技術で誕生したのではなく,C-Media Electronicsが,Intelのガイドラインに従ったDSP内蔵CODECの第1世代なり,それに近いチップをいち早く搭載することで,今回紹介したような仕様を獲得したのではないだろうか。
Intelのガイドラインに従って製造された新世代のCODECを搭載すれば,DSP機能により,「ただサウンド入出力ができる」以上のことを,CPU負荷を(なるべく)かけずに行えるようになる。今後,各社のヘッドセット製品中上位モデルや,場合によっては高価格帯のマザーボードなども,この新世代CODECを採用していく可能性が高そうだ。いよいよ,ゲーム用途での単体サウンドカードは,役目を完全に終えるときが来るのかもしれない。
■マイク特性の測定方法
マイクの品質評価に当たっては,周波数と位相の両特性を測定する。測定に用いるのは,イスラエルのWaves Audio製オーディオアナライザソフト「PAZ Psychoacoustic Analyzer」(以下,PAZ)。筆者の音楽制作用システムに接続してあるスピーカー(ADAM製「S3A」)をマイクの正面前方5cmのところへ置いてユーザーの口の代わりとし,スピーカーから出力したスイープ波形をヘッドセットのマイクへ入力。入力用PCに取り付けてあるサウンドカード「Sound Blaster X-Fi
PAZのデフォルトウインドウ。上に周波数,下に位相の特性を表示するようになっている
Titanium」とヘッドセットを接続して,マイク入力したデータを
PAZで計測するという流れになる。もちろん事前には,カードの入力周りに位相ズレといった問題がないことを確認済みだ。
測定に利用するオーディオ信号はスイープ波形。これは,サイン波(※一番ピュアな波形)を20Hzから24kHzまで滑らかに変化させた(=スイープさせた)オーディオ信号である。スイープ波形は,テストを行う部屋の音響特性――音が壁面や床や天井面で反射したり吸収されたり,あるいは特定周波数で共振を起こしたり――に影響を受けにくいという利点があるので,以前行っていたピンクノイズによるテスト以上に,正確な周波数特性を計測できるはずだ。
またテストに当たっては,平均音圧レベルの計測値(RMS)をスコアとして取得する。以前行っていたピークレベル計測よりも測定誤差が少なくなる(※完全になくなるわけではない)からである。
結局のところ,「リファレンスの波形からどれくらい乖離しているか」をチェックするわけなので,レビュー記事中では,そこを中心に読み進め,適宜データと照らし合わせてもらいたいと思う。
用語とグラフの見方について補足しておくと,周波数特性とは,オーディオ機器の入出力の強さを「音の高さ」別に計測したデータをまとめたものだ。よくゲームの効果音やBGMに対して「甲高い音」「低音」などといった評価がされるが,この高さは「Hz」(ヘルツ)で表せる。これら高域の音や低域の音をHz単位で拾って折れ線グラフ化し,「○Hzの音は大きい(あるいは小さい)」というためのもの,と考えてもらえばいい。人間の耳が聴き取れる音の高さは20Hzから20kHz(=2万Hz)といわれており,4Gamerのヘッドセットレビューでもこの範囲について言及する。
周波数特性の波形の例。実のところ,リファレンスとなるスイープ信号の波形である
上に示したのは,PAZを利用して計測した周波数特性の例だ。グラフの左端が0Hz,右端が20kHzで,波線がその周波数における音の大きさ(「音圧レベル」もしくは「オーディオレベル」という)を示す。また一般論として,リファレンスとなる音が存在する場合は,そのリファレンスの音の波形に近い形であればあるほど,測定対象はオーディオ機器として優秀ということになる。
ただ,ここで注意しておく必要があるのは,「ヘッドセットのマイクだと,15kHz以上はむしろリファレンス波形よりも弱めのほうがいい」ということ。15kHz以上の高域は,人間の声にまず含まれない。このあたりをマイクが拾ってしまうと,その分だけ単純にノイズが増えてしまい,全体としての「ボイスチャット用音声」に悪影響を与えてしまいかねないからだ。男声に多く含まれる80〜500Hzの帯域を中心に,女声の最大1kHzあたりまでが,その人の声の高さを決める「基本波」と呼ばれる帯域で,これと各自の声のキャラクターを形成する最大4kHzくらいまでの「高次倍音」がリファレンスと近いかどうかが,ヘッドセットのマイク性能をチェックするうえではポイントになる。
位相は周波数よりさらに難しい概念なので,ここでは思い切って説明を省きたいと思う。PAZのグラフ下部にある半円のうち,弧の色が青い部分にオレンジ色の線が入っていれば合格だ。「AntiPhase」と書かれている赤い部分に及んでいると,左右ステレオの音がズレている(=位相差がある)状態で,左右の音がズレてしまって違和感を生じさせることになる。
位相特性の波形の例。こちらもリファレンスだ
ヘッドセットのマイクに入力した声は仲間に届く。それだけに,違和感や不快感を与えない,正常に入力できるマイクかどうかが重要となるわけだ。
- 関連タイトル:
 SteelSeries
SteelSeries
- この記事のURL:
Copyright 2010 SteelSeries Aps